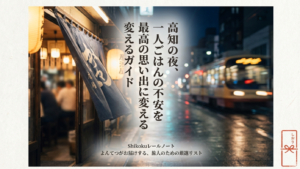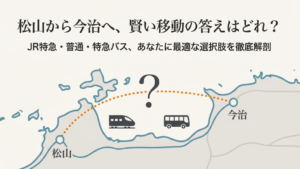JR四国の路線を旅していると、ほとんどの場所で列車がすれ違うために駅で停車することに気づくかもしれません。「JR四国の複線区間は、いったいどこにあるのだろう?」と疑問に思ったことはありませんか。
実は、JR四国に存在する本格的な複線区間は、予讃線のごく一部、高松駅と多度津駅の間に限られています。この記事では、JR四国で「唯一」と言えるこの複線区間の詳細と、なぜこの区間だけが特別に複線化されたのか、その歴史的な背景や重要性を深く掘り下げていきます。
さらに、なぜ他の主要な路線が単線のままなのか、その根本的な理由をコストや需要、地形といった多角的な視点から徹底解説。単線が基本であることによる列車のダイヤへの影響や、今後の複線化の可能性についても、分かりやすく説明します。この記事を読めば、JR四国の鉄道網が持つ特徴とその背景にある事情のすべてが明確になります。
- JR四国で唯一の複線区間である予讃線(高松~多度津)の場所と役割
- なぜ他の路線は複線化されず、ほぼ全線が単線のままなのかという理由
- 唯一の複線区間がJR四国の列車運行において果たしている重要な役割
- 複線と単線が混在することで生まれるダイヤ編成上の特徴
JR四国の「唯一の」複線区間と基本知識

- 単線と複線の違いと現状
- JR四国唯一の複線区間:予讃線
- 予讃線(高松~多度津)の重要性
- 複線化が高松都市圏に集中する理由
- 複線が採用されている理由とその効果
- なぜ「唯一」なのか?他の路線が単線の理由
単線と複線の違いと現状
鉄道の線路には、大きく分けて「単線」と「複線」の2種類が存在します。これらの違いを理解することが、JR四国の鉄道事情を知る上での第一歩となります。
要するに、単線とは上下線で1本の線路を共有する方式です。そのため、反対方向から来る列車とすれ違うためには、駅などに設けられた「交換設備(行き違い施設)」でどちらかの列車が待機する必要があります。日本の地方交通線では、この単線方式が広く採用されています。
一方、複線は上り線用と下り線用にそれぞれ専用の線路が敷設されている方式を指します。これにより、列車は駅で待つことなくすれ違うことが可能で、より多くの列車をスムーズに運行させられます。
現在のJR四国では、後述する特定の区間を除いた、ほぼ全ての路線が単線で運行されています。これが、四国内を旅する際に、特急列車が対向列車を待つために駅で数分間停車する光景に頻繁に出会う理由です。
JR四国唯一の複線区間:予讃線
それでは、JR四国に存在する唯一の本格的な複線区間はどこなのでしょうか。その答えは「予讃線の高松駅から多度津駅までの区間」です。
| 路線名 | 複線区間 | 全長 | 区間の特徴 |
| 予讃線 | 高松駅 ~ 多度津駅 | 32.7km | 四国の玄関口である高松市と西讃地域を結ぶ最重要幹線。本州と四国を結ぶ列車の多くがこの区間を走行する。 |
以前は他の路線にも部分的な複線区間があるとされていましたが、それらは駅構内やごく短い単線並列区間であり、路線全体の輸送を担う連続した「複線区間」とは性質が異なります。したがって、JR四国の鉄道網を語る上で、複線区間はこの予讃線の高松~多度津間のみと考えるのが最も正確な理解となります。
役立つ参考記事:JR四国 電化区間の特徴と非電化区間の違いを紹介
予讃線(高松~多度津)の重要性

なぜ、この予讃線(高松~多度津)だけが特別に複線化されているのでしょうか。その理由は、この区間がJR四国全体にとって、まさに「心臓部」と言えるほどの重要性を持っているからです。
第一に、この区間は四国の経済・行政の中心地である高松市と、坂出市、丸亀市といった西讃の主要都市を結ぶ、最も利用者の多い通勤・通学路線です。朝夕のラッシュ時には、快速「サンポート」や普通列車が数分おきに運行されており、この高頻度運転を支えるためには複線が不可欠です。
第二に、本州と四国を結ぶ瀬戸大橋線からの列車が乗り入れる、四国の玄関口としての役割があります。岡山方面からの快速「マリンライナー」や寝台特急「サンライズ瀬戸」は、すべてこの区間を通って高松駅へと向かいます。
さらに、多度津駅は高知方面へ向かう土讃線との分岐点でもあります。つまり、岡山・高松方面から松山方面、高知方面へと向かう特急列車がすべてこの区間に集中するのです。このように、JR四国の主要な旅客流動が一点に集約されるため、線路容量に余裕のある複線でなければ到底さばききれない、というのが実情です。
複線化が高松都市圏に集中する理由
前述の通り、JR四国の複線区間は高松都市圏に完全に集中しています。これは、四国内の他のエリアと比較して、人口、経済活動、そして交流人口がこの地域に突出して多いことが最大の理由です。
高松市は香川県の県庁所在地であるだけでなく、国の出先機関や大企業の四国支社が集中する「四国の頭脳」とも言える都市です。そのため、鉄道利用を前提としたビジネス需要や通勤・通学需要が、他の都市圏とは桁違いに大きいのです。
この需要に応え、安定した大量輸送を実現するために、鉄道インフラへの投資も必然的にこのエリアに重点的に行われてきました。唯一の複線区間が存在するという事実は、高松都市圏がJR四国にとっても、また四国全体の経済にとっても、いかに重要な場所であるかを物語っています。
複線が採用されている理由とその効果

予讃線の特定区間で複線が採用されている理由は、主に「輸送力の増強」と「運行速度の向上」という2つの大きなメリットからもたらされる効果にあります。
第一に、複線化によって線路の容量が大幅に増え、より多くの列車を運行できるようになります。単線では対向列車との行き違いのために駅での停車が必須ですが、複線ではその必要がありません。これにより、ラッシュ時のような需要が高い時間帯でも、列車を次々と運行することが可能になるのです。
第二に、追い越しが容易になるため、全体のスピードアップが図れます。例えば、速度の速い特急「しおかぜ」や「いしづち」が、前を走る普通列車を追い越す際、単線では普通列車が駅で待避する必要があります。しかし、複線であれば、普通列車が走行を続けながら特急列車が別の線路を使って追い越すことができ、特急列車の所要時間短縮に繋がります。
これらの効果から、JR四国では利用者が最も多く、最重要列車が集中する予讃線の高松~多度津間において、安定した大量輸送と速達性を両立させるために複線が採用されているわけです。
なぜ「唯一」なのか?他の路線が単線の理由
ではなぜ、複線区間はこの予讃線の一区間「唯一」なのでしょうか。他の主要路線、例えば高徳線や土讃線、予讃線の松山近郊などが単線のままなのは、主に3つの理由が複合的に絡み合っているからです。
1. 莫大な建設コスト
最大の理由は、複線化にかかる費用が非常に高額であることです。新たに線路を1本敷設するには、用地の買収、トンネルや橋梁の建設または改築、信号設備の更新など、莫大な投資が必要となります。JR四国の経営規模で、複数の路線を複線化するのは現実的ではありません。
2. 費用対効果の問題
鉄道事業は、投資したコストに見合うだけの収益(運賃収入)が見込めるかどうかが常に問われます。予讃線の高松~多度津間は、その投資に見合うだけの圧倒的な輸送需要がありますが、他の区間ではそこまでの需要が見込めません。人口密度が比較的低く、モータリゼーション(自動車社会化)が進んでいるため、多額の費用を投じて複線化しても、採算が取れないのです。
3. 地形的な制約
四国は山がちな地形が多く、平野部が少ないという地理的な特徴も、複線化を難しくしている一因です。特に土讃線が横断する四国山地や、海岸沿いの険しい地形に新たに線路を敷設するには、大規模なトンネルや橋を建設する必要があり、平地に建設するよりもさらにコストが膨らみます。
これらの理由から、複線化は、需要、採算性、地形の全ての条件をクリアできた、予讃線の高松~多度津間に限定されているのです。

唯一の複線区間の歴史と単線が基本の鉄道網

- 予讃線複線化の歴史的経緯
- 複線区間と単線区間のダイヤ比較
- 今後の複線化の可能性は限りなく低い
予讃線複線化の歴史的経緯
JR四国唯一の複線区間である予讃線・高松~多度津間は、一朝一夕に完成したわけではありません。その歴史は国鉄時代にまで遡り、四国の発展と共に段階的に整備が進められてきました。
複線化の最大の契機となったのは、1988年の瀬戸大橋開通です。これにより、本州と四国が鉄道で直接結ばれ、人や物の流れが劇的に変化しました。本州からの玄関口となる坂出・高松エリアの輸送力増強は、JR四国にとって最重要課題となったのです。
この歴史的な出来事に対応するため、瀬戸大橋開通とそれに続く1990年代にかけて、予讃線の複線化工事が急ピッチで進められました。特に、1993年の予讃線・高松駅から伊予市駅までの電化は、複線化と合わせて行われた一大プロジェクトです。電化による列車の高速化と、複線化による高頻度運転の実現が組み合わさることで、現在の便利で高速な予讃線の姿が形作られました。
このように、予讃線の複線区間は、瀬戸大橋開通という国家的なプロジェクトと連動し、四国の近代化を象徴するインフラとして整備されてきた歴史を持っています。
複線区間と単線区間のダイヤ比較

唯一の複線区間と、その他の広大な単線区間が混在していることは、JR四国の列車運行計画、すなわち「ダイヤ」に大きな特徴を与えています。
予讃線の高松~多度津間の複線区間では、対向列車を気にすることなくダイヤを組めるため、非常に柔軟な運行が可能です。ラッシュ時には普通・快速・特急といった多種多様な列車が、まるで都市部の鉄道のようにスムーズに行き交います。万が一、ある列車に遅れが発生しても、後続の列車が追い越すなどして影響を最小限に食い止め、遅れを回復させやすいという強みもあります。
一方で、この区間を抜けて単線区間に入ると、状況は一変します。例えば、多度津から松山方面へ向かう特急「いしづち」は、単線区間では必ずどこかの駅で対向の特急列車とすれ違う必要があります。このすれ違いの時刻と場所は厳密に決まっているため、もし対向列車が少しでも遅れると、その影響を直接受けてこちらの列車も遅れてしまいます。一つの遅延が、まるでドミノ倒しのように路線全体に波及しやすいのが単線区間の弱点です。
JR四国を利用する際は、この複線区間でのスムーズな走行と、単線区間での味わい深い行き違い待ちの両方を体験することができ、その対比が鉄道の面白さを教えてくれます。
今後の複線化の可能性は限りなく低い
「将来、予讃線の他の区間や、別の路線が複線化される可能性はあるのだろうか?」これは多くの鉄道ファンが抱く期待かもしれませんが、残念ながらその可能性は限りなく低いと言わざるを得ません。
最大の理由は、日本の深刻な人口減少と少子高齢化です。今後、四国の人口が大幅に増加に転じることは考えにくく、鉄道利用者が爆発的に増える見込みもありません。このような社会状況で、莫大なコストがかかる新規の複線化プロジェクトに投資するという経営判断は、極めて困難です。
JR四国が現在進めているのは、新たな線路を建設する「ハード」面の投資よりも、既存の設備を有効活用し、サービスの質を高める「ソフト」面の取り組みです。例えば、チケットアプリ「しこくスマートえきちゃん(スマえき)」の導入や、快適な新型車両への置き換えなどがそれに当たります。
したがって、当面は、既存の唯一の複線区間である予讃線(高松~多度津)を最大限に活用し、広大な単線ネットワークと組み合わせることで、効率的かつ持続可能な鉄道網を維持していくことが、JR四国の現実的な方針となるでしょう。
これからのJR四国の複線区間の役割
- JR四国の本格的な複線区間は予讃線の高松駅から多度津駅間のみ
- 上記以外の路線は駅構内などを除きすべて単線で運行されている
- 予讃線の当該区間は四国で最も利用者が多く、最重要列車が集中する
- 本州と四国を結ぶ列車も全てこの唯一の複線区間を通過する
- 複線であることでラッシュ時の高頻度運転や特急の高速運転が可能になる
- 他の路線が単線なのは建設コスト、採算性、地形的な制約が理由
- 予讃線の複線化は瀬戸大橋開通と連動した歴史的なプロジェクトだった
- 複線区間の柔軟なダイヤが単線区間の定時運行を支える側面もある
- 観光列車も運行の起点では複線区間の恩恵を受けている
- 人口減少などを背景に、今後新たな複線化の可能性は極めて低い
- JR四国は既存インフラの有効活用とサービス向上に注力している
- 唯一の複線区間は四国の経済と人々の移動を支える大動脈である
- この区間はJR四国の鉄道網において心臓部とも言える役割を担う
- 単線と複線の対比を知ることでJR四国の旅はより深みを増す
- 今後もこの唯一の複線区間は大切に維持・活用されていく