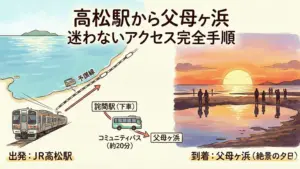特急しおかぜの予約や乗車を考えたとき、「どの車両に乗ればいいのだろう?」「編成が複雑でよく分からない」と感じたことはありませんか。特急しおかぜの車両編成パターンは一見すると難解に思えるかもしれませんが、その仕組みを理解すれば、旅の計画はもっとスムーズで快適になります。
この記事では、車両編成とは何かという基本的な解説から始め、使用される車両形式である8000系と8600系の詳細な違い、そして多くの人が疑問に思う「しおかぜ」と「いしづち」の併結運転パターンまで、分かりやすく解き明かします。
さらに、グリーン車はどこにあるのかという座席配置、自由席と指定席の位置と特徴、乗り換えに便利な編成の見分け方といった実用的な情報も網羅。先頭車両はどっち向きかという進行方向の確認方法や、平日と休日での編成の違い、多客期に変わる臨時編成の特徴にも触れることで、あらゆる状況に対応できる知識が身につきます。この記事を読めば、乗車時の失敗や後悔を防ぎ、あなたの四国旅行をより一層素晴らしいものにできるはずです。
- 2種類の車両(8000系・8600系)の編成パターンと特徴
- 「しおかぜ」と「いしづち」の連結・切り離しの仕組み
- グリーン車・指定席・自由席の号車と座席配置
- 状況に応じた編成の見分け方と便利な乗車テクニック
基本から解説!特急しおかぜ車両編成パターン

この章では、特急しおかぜを理解する上で基本となる編成の仕組みや、運用される車両形式、そして特徴的な運転形態について解説します。
- 車両編成とは?基本パターンを解説
- 使用される車両形式(8000系・8600系)
- しおかぜといしづちの併結運転パターン
- グリーン車はどこ?座席配置
- 自由席と指定席の位置と特徴
車両編成とは?基本パターンを解説

特急しおかぜの「車両編成」とは、列車を構成する車両の組み合わせや順序のことを指します。この編成パターンは、実は非常に合理的で、モジュール化された基本単位を組み合わせることで成り立っています。
しおかぜの運用を支えるのは、主に8000系電車に用いられる2種類の基本編成です。
- L編成 (Long編成):
5両で構成される編成で、特急「しおかぜ」の主体となります。1号車から5号車までで成り立ち、グリーン車を含むため、サービスの中心を担う編成と考えられます。 - S編成 (Short編成):
3両で構成される短い編成です。主に高松方面の特急「いしづち」として運用されますが、列車によってはこのS編成が単独で「しおかぜ」として走るケースもあります。
このように、5両と3両という決まった長さの編成を基本単位(モジュール)としています。このため、需要に応じてこれらを連結したり、単独で運転したりと、柔軟な運用が可能になるのです。例えば、多くの列車がL編成とS編成を連結した8両編成で運転され、輸送力を確保しています。
使用される車両形式(8000系・8600系)
現在の特急しおかぜには、特性の異なる2つの世代の車両が使用されています。それが「8000系」と「8600系」です。どちらの車両に乗車するかで、車内設備や快適性が異なるため、その違いを知っておくことが大切です。
8000系:進化を続ける主力車両
長年にわたり、しおかぜの顔として活躍してきたのが8000系です。カーブの多い予讃線を高速で走行するため、「制御付自然振子装置」という車体を傾けるシステムを備えているのが大きな特徴です。
2023年からは大規模なリニューアル工事が順次進められており、サービス品質が大幅に向上しています。リニューアルされた車両では、指定席の全席と自由席の窓側にコンセントが設置されました。ただし、2027年度の完了までは未更新の車両も混在して走るため、乗車する列車がどちらのタイプかによって設備に差がある点には注意が必要です。
また、8000系の一部には、子どもたちに大人気の「アンパンマン列車」仕様の編成も存在します。特定の列車の1号車指定席は「アンパンマンシート」となっており、家族連れには特におすすめできます。

8600系:快適性を追求した最新鋭車両
2014年に登場したJR四国の最新鋭特急車両が8600系です。現在、1日4往復のしおかぜに限定して、固定で運用されています。
蒸気機関車をモチーフにした個性的な先頭デザインが目を引きますが、最大の魅力はその優れた快適性にあります。普通車を含めた全座席にコンセントが完備されているため、移動中にPCやスマートフォンを充電したい方には最適です。
グリーン車は1列+2列の豪華なシートで、電動レッグレストも備わっています。普通車もシートの色が号車ごとに異なり、細部までこだわったデザインが特徴です。より快適な移動を求めるのであれば、8600系で運転される列車を選ぶのが賢明な選択と言えます。
| 項目 | 8000系 | 8600系 |
| 車体傾斜システム | 制御付自然振子式 | 空気バネ式 |
| コンセント(普通車) | リニューアル車: 指定席全席、自由席窓側 未更新車:なし | 全座席に設置 |
| グリーン車設備 | リニューアル車:電動レッグレスト 未更新車: – | 電動レッグレスト、可動式枕 |
| 車いす対応設備 | 1・4・6号車に分散 | 5号車に集約 |
| 主な充当列車 | しおかぜ ・いしづち 1~6,9~10,13~18,21,22,25~30号 | しおかぜ・いしづち 7,8,11,12,19,20,23,24号など |

しおかぜといしづちの併結運転パターン

特急しおかぜの運用で最も特徴的なのが、高松発着の特急「いしづち」との併結(連結)運転です。これは、岡山方面と高松方面という2つの主要なルートからの乗客を、1本の列車で効率よく運ぶための非常に洗練された仕組みです。
この連結・切り離し作業は、香川県の宇多津駅または多度津駅で行われます。
- 下り(松山方面):
岡山から来た「しおかぜ」と高松から来た「いしづち」が宇多津駅(または多度津駅)で連結し、1本の列車となって松山へ向かいます。このとき、岡山からの「しおかぜ」(1~5号車)が進行方向の先頭(松山寄り)になります。 - 上り(岡山・高松方面):
松山から来た列車が宇多津駅(または多度津駅)で切り離されます。前方の車両が「しおかぜ」として岡山へ、後方の車両が「いしづち」として高松へと、それぞれの目的地へ分かれて走行します。
このシステムにより、ほとんどの列車が8両(8000系L編成+S編成)または7両(8600系)という長い編成で予讃線を走ります。乗客にとっては、岡山・高松のどちらから乗っても松山まで乗り換えなしで行けるという大きなメリットがあるのです。
グリーン車はどこ?座席配置

グリーン車を利用したい場合、号車を迷う必要はありません。特急しおかぜのグリーン車は、使用される車両形式(8000系・8600系)や列車の号数に関わらず、必ず1号車の半室に設置されています。
1号車の半分がグリーン車、もう半分が普通車指定席という構造です。岡山・松山間の全区間を走る「しおかぜ」には、全ての列車にこのグリーン車が連結されています。そのため、どの列車を選んでも上質な空間で移動することが可能です。
ただし、グリーン車の設備は車両形式によって異なります。
- 8600系: 座席が「1列+2列」の3列配置で、定員はわずか12名です。全席に電動レッグレストや読書灯が完備され、非常にプライベートで豪華な空間が提供されます。
- 8000系: 座席は「2列+2列」の4列配置です。8600系ほどの豪華さはありませんが、普通席に比べてシートピッチが広く、ゆったりと過ごせます。リニューアルにより内装も一新され、快適性は向上しています。
より上質なサービスを求めるのであれば、8600系で運行される列車を選ぶと満足度が高まるでしょう。
自由席と指定席の位置と特徴
特急しおかぜの普通席は、自由席と指定席に分かれています。これらの座席がどの号車にあるのかは、基本的なパターンを覚えておくと便利です。
基本的な座席配置
標準的な8両編成(8000系L編成+S編成)の場合、座席の配置は以下のようになっています。
- 指定席: 主に松山寄りの1号車(半室)、2号車、3号車と、編成の最後尾にあたる8号車に設定されています。
- 自由席: 中間の4号車、5号車、6号車、7号車に設定されているのが一般的です。
8600系で運転される場合、指定席の割合が多くなる傾向があります。例えば5両編成の「しおかぜ」部分では、4号車以外は全て指定席です。
注意点:繁忙期の変更
基本的な配置は上記の通りですが、注意したいのがゴールデンウィークやお盆、年末年始などの繁忙期です。多くの人が利用する時期には、着席して移動したいという需要が高まります。
そのため、JR四国では、これらの多客期に自由席の一部車両を「指定席」に変更する措置を取ることがあります。普段は自由席の4号車や5号車が指定席として販売される場合があるのです。旅行の計画を立てる際は、最新の情報をJRのウェブサイトなどで確認するか、予約時に座席種別をしっかり確認することが大切です。確実に座りたい場合は、時期に関わらず指定席を予約するのが最も確実な方法です。
乗る前に確認!特急しおかぜ車両編成パターン活用術

ここからは、実際の乗車時に役立つ、より実践的な情報や注意点を解説します。編成パターンを知ることで、乗り間違いを防ぎ、より快適な旅を計画できます。
- 先頭車両はどっち向き?進行方向の確認方法
- 乗り換えに便利な編成パターンの見分け方
- 平日と休日で異なる?編成の違い
- 多客期に変わる?臨時編成の特徴
- まとめ:特急しおかぜ車両編成パターンの要点
先頭車両はどっち向き?進行方向の確認方法
ホームで列車を待つ際、「どちら向きの列車だろう?」と迷わないために、号車番号のルールを覚えておくと非常に便利です。特急しおかぜには、列車の進行方向に関わらず常に守られる大原則があります。
それは、「松山方面の先頭車両が1号車になる」というルールです。
このため、岡山から松山へ向かう下り列車では、1号車が列車の先頭になります。ホームで待つ際は、進行方向の最も前に1号車が来ると考えておけば間違いありません。
一方で、注意が必要なのが松山から岡山へ向かう上り列車です。この場合も「松山方面が1号車」のルールは変わりません。したがって、上り列車では1号車が編成の最も後ろ(最後尾)になります。指定席券に「1号車」と書かれている場合、ホームの岡山寄り先端で待っていると、全く逆の方向へ長距離を歩くことになりかねません。
駅の電光掲示板やホームの乗車口案内には、各号車の停車位置が示されています。特に上り列車に乗車する際は、これらの案内を事前にしっかりと確認し、自分が乗るべき号車がホームのどのあたりに停まるのかを把握しておくことが、スムーズな乗車の鍵となります。
乗り換えに便利な編成パターンの見分け方
特急しおかぜの複雑な編成パターンは、特に「いしづち」と連結して走る区間で乗り間違いの原因になることがあります。しかし、いくつかのポイントを押さえることで、簡単に見分けることが可能です。
8000系(8両編成)の場合
最も標準的な8両編成では、1号車から5号車が岡山発着の「しおかぜ」、6号車から8号車が高松発着の「いしづち」です。自分がどちらの目的地へ向かうのか、またはどちらから乗ってきたのかによって、乗るべき車両群が明確に分かれています。宇多津駅や多度津駅での乗り過ごしを防ぐため、自分の切符に書かれた号車番号を必ず確認しましょう。
8600系(7両編成)の注意点
最新鋭の8600系に乗車する際は、一つユニークな特徴を知っておくと混乱を避けられます。この車両が「いしづち」と連結する際、「しおかぜ」部分は1~5号車、「いしづち」部分は6号車と8号車で運転されます。
そう、「7号車が存在しない」のです。
これは、JRの予約システムがより一般的な8両編成を基準にしているため、システム上の整合性を保つための工夫です。物理的には6両目の隣に7両目にあたる車両があるのですが、その車両には「8号車」という番号が与えられています。初めて乗る方は「なぜ7号車がないんだろう?」と不思議に思うかもしれませんが、これは故障や欠車ではなく、8600系特有の運用上のルールなのです。この点を理解しておけば、ホームでの戸惑いをなくすことができます。

平日と休日で異なる?編成の違い

特急しおかぜの運用について、「平日は短い編成で、休日は長くなるのでは?」と考える方もいるかもしれません。
しかし、特急しおかぜの場合、基本的な車両編成や連結パターンは平日と休日で変わりません。どの列車に8000系が使われ、どの列車に8600系が使われるかという充当計画は、曜日に関わらず固定されています。したがって、「月曜日だから短い」とか「土曜日だから必ず8600系だ」ということはありません。
これは、日々の通勤・ビジネス利用と、週末の観光利用の双方に安定して対応するための運用方針と考えられます。年間を通じて、どの曜日に乗っても同じサービスレベルと輸送力が提供される安定性が、特急しおかぜの信頼性を支えています。
ただし、これはあくまで原則です。ごく稀に、車両の定期検査や急な故障などの理由で、予定されていた車両とは異なる車両が代走で運用される可能性はゼロではありません。例えば、本来8600系が走るはずの列車に8000系が使用されるといったケースです。どうしても特定の車両に乗りたい場合は、複数の候補日を検討するのも一つの方法かもしれません。
多客期に変わる?臨時編成の特徴
ゴールデンウィーク、お盆、年末年始といった多くの人が移動する「多客期」には、特急しおかぜの編成は通常期と異なる特徴を見せます。
前述の通り、この時期に最も大きな変化が見られるのは、座席種別の変更です。普段は自由席として運用されている4号車や5号車といった車両が、「全席指定席」として販売されることがあります。これは、長距離を確実に座って移動したいという乗客のニーズに応えるための措置です。
このため、多客期に自由席を利用しようと考えている場合は注意が必要です。いざ乗ろうとしたら自由席が1~2両しかなく、満席で座れないという事態も起こり得ます。多客期の旅行を計画する際は、早めに指定席を予約することが、快適な旅を始めるための最も確実な方法となります。
かつては車両を1両増結するといった対応も見られましたが、現在の運用では基本編成(L編成・S編成)が確立されているため、座席種別を変更することで需要の変動に柔軟に対応するのが主流です。この運用方法は、車両数を増やすことなく、効率的に収益性と顧客満足度を高めるための合理的な戦略と言えます。
まとめ:特急しおかぜ車両編成パターンの要点
この記事で解説してきた、特急しおかぜの車両編成パターンに関する重要なポイントを以下にまとめます。これらの要点を押さえておけば、あなたの「しおかぜ」利用がより一層スムーズで快適になるはずです。
- 特急しおかぜの車両は8000系と8600系の2種類
- 8000系は5両のL編成と3両のS編成が基本ユニット
- 8600系は全席コンセント完備の最新鋭車両
- 8000系はリニューアルが進みサービス品質が向上中
- 一部の8000系はアンパンマン列車として運行
- 大半の列車は高松発着の特急いしづちと併結運転
- 連結と切り離しは主に香川県の宇多津駅で行われる
- 列車の進行方向は常に松山方面の先頭が1号車
- 岡山方面へ向かう上り列車では1号車が最後尾になる
- グリーン車は全列車で1号車の半分に設置されている
- 指定席は主に1~3号車と8号車に設定
- 自由席は主に中間の4~7号車に設定
- 8600系併結時は7号車が存在しない点に注意
- コンセントを確実に使いたい場合は8600系が最適
- 多客期には自由席の一部が指定席に変更されることがある