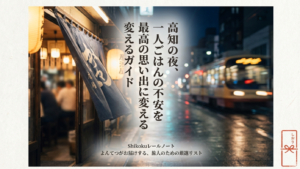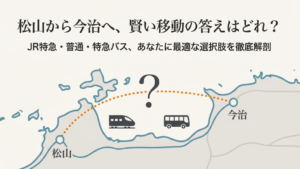JR四国の最新鋭特急気動車、2700系。その編成を見たとき、「なぜ中間車がないのだろう?」と疑問に思ったことはありませんか。実は、2700系に中間車が存在しない理由には、JR四国ならではの緻密な戦略が隠されています。この記事では、2700系がなぜ全車両先頭車というユニークな構成を採用したのか、その核心に迫ります。
本稿では、2両1ユニット方式の採用背景や、気動車で中間車を持たないメリットを深掘りします。また、先代車両との比較を通じて、失敗から学んだ2600系との設計思想の違いや、伝統を受け継いだ旧2000系の中間車との比較も行います。
さらに、2700系の編成バリエーションの豊かさや、実際の増結時の運用スタイルを紹介し、先頭車のみで構成されるメリット・デメリットを多角的に考察します。この記事を最後まで読めば、今後中間車が製造される可能性や、2700系が四国の鉄道に与えた影響まで、あなたの疑問がすべて解消されるはずです。
- 2700系が中間車を持たない戦略的な理由
- 先代車両から受け継いだ技術と独自の進化
- 全先頭車構成が可能にする柔軟な運用方法
- 今後の展望と四国の鉄道網における役割
なぜ?2700系の中間車の不在が示す設計思想
このセクションでは、2700系がなぜ中間車を持たないという設計思想に至ったのか、その根幹にある理由を多角的に解説します。
- 2700系に中間車が存在しない理由とは
- 気動車で中間車を持たないメリットを解説
- 先頭車のみで構成されるメリット・デメリット
- 柔軟性を生む2両1ユニット方式の採用背景
- 失敗から学ぶ2600系との設計思想の違い
- 伝統と革新、旧2000系の中間車との比較
2700系に中間車が存在しない理由とは

2700系に中間車が存在しない最大の理由は、JR四国の路線環境と経営戦略に最適化された「運用の柔軟性」を極限まで高めるためです。
四国島内の特急列車は、高松や岡山といった主要都市と地方都市を結ぶ中で、区間によって旅客需要が大きく変動する特性を持っています。例えば、土讃線の特急「南風」は、多客期には5両編成で運転されることがありますが、途中の宇多津駅や高知駅で編成を分割し、それぞれ別の列車として運行するケースが頻繁に見られます。
もし編成内に運転台のない中間車が存在すると、このような機動的な分割・併合は不可能になります。全車両が運転台を持つ先頭車仕様であるからこそ、需要に応じて編成を2両、3両、5両と自在に組み替えることができ、輸送力を最適化できるのです。これにより、利用者の少ない区間で不要な車両を走らせる無駄を省き、エネルギー効率の向上とメンテナンスコストの削減を両立させています。

気動車で中間車を持たないメリットを解説
気動車、特に2700系のように全車両が動力を持つ編成で中間車をなくすことには、いくつかの明確なメリットがあります。
第一に、資産効用の最大化が挙げられます。鉄道車両は非常に高価な資産であり、その稼働率を高めることが経営の効率化に直結します。中間車を含む固定的な編成では、1両でも不具合が起きると編成全体が運用から外れてしまうことがあります。しかし、2700系のように全車両が独立して走行可能なユニットであれば、どの車両も遊休資産になることなく、常に稼働させることが可能です。つまり、保有する車両数を最小限に抑えつつ、路線網全体のサービスを維持できるのです。
第二に、メンテナンスの計画性が向上します。どの車両もほぼ均等に使用されるため、走行距離や部品の消耗度合いが平準化され、検査や修繕の計画を立てやすくなります。これもまた、長期的なコスト削減に繋がる重要な要素です。
先頭車のみで構成されるメリット・デメリット

全車両が先頭車で構成される設計には、多くのメリットがある一方で、考慮すべきデメリットも存在します。
メリット
前述の通り、最大のメリットは運用上の圧倒的な柔軟性です。需要に応じた増解結が容易で、輸送力をきめ細かく調整できます。また、編成の向きを問わず運用できるため、終着駅での折り返し作業が迅速に行える点も利点です。さらに、万が一いずれかの車両の運転台に不具合が発生しても、編成を組み替えたり、反対側の運転台を使用したりすることで運行を継続できる冗長性の高さも持っています。
デメリット
一方、デメリットとしては、製造コストの増加が挙げられます。運転台は精密な機器の集合体であり、これを全車両に搭載すると、運転台のない中間車を製造するよりも1両あたりの単価は高くなります。また、運転台が客室スペースを占有するため、同じ車体長の中間車と比較すると座席定員が若干少なくなります。長期的に見れば、運転台関連機器のメンテナンス費用が全車両分発生することも、コスト面の課題と言えるかもしれません。
柔軟性を生む2両1ユニット方式の採用背景
2700系は、基本的に2両を1つのユニットとして運用されることが多くなっています。この「2両1ユニット」という考え方は、運用の柔軟性を確保するための基本的な構成単位です。
この背景には、効率的な運行を維持するための実際的な理由があります。1両での単独運行も理論上は可能ですが、終着駅で折り返す際に方向転換が必要になるなど、現実的ではありません。そこで、上り向きの2700形と下り向きの2750形または2800形を組み合わせた2両編成を基本とすることで、どの駅でもスムーズな折り返し運転が可能になります。
この2両ユニットが、いわば「基本ブロック」の役割を果たします。需要が少ない区間ではこの基本ブロックで運行し、利用者が増える区間や時間帯には、このブロックをもう一つ連結して4両にしたり、中間に1両増結して3両や5両にしたりします。このように、2両という最小単位を組み合わせる設計思想が、2700系の柔軟な運用スタイルの根幹を支えているのです。
失敗から学ぶ2600系との設計思想の違い

2700系の設計思想を理解する上で、先行試作車である2600系の存在は欠かせません。2700系は、2600系の経験から得た重要な教訓を生かして誕生しました。
設計思想の最も大きな違いは、車体傾斜装置にあります。2600系では、構造がシンプルでコスト面に優れるとされる「空気ばね式車体傾斜装置」が採用されました。しかし、カーブが連続する土讃線での走行試験において、空気の補充が追いつかずに傾斜性能を維持できないという致命的な課題が判明したのです。
この結果を受け、JR四国は2600系の量産を断念し、2700系の開発へと舵を切りました。2700系では、エンジンや車体といった近代的なプラットフォームは2600系のものを継承しつつ、車体傾斜装置は、2000系で30年近い実績と信頼性を持つ「制御付き自然振り子装置」に回帰しました。これは、最新技術であっても自社の路線環境に適さなければ採用しないという、実用性を最優先するJR四国の現実主義的な開発哲学を明確に示しています。2700系は、失敗から学び、実証された技術と新しい技術を融合させた、確実な進化形なのです。


伝統と革新、旧2000系の中間車との比較
2700系の直接の置き換え対象となった旧2000系は、世界で初めて制御付き自然振り子式気動車を実用化した画期的な車両でした。この2000系には、運転台のない中間車(2150形グリーン車や2200形普通車など)が存在していました。
2000系もまた、増解結による柔軟な運用を行っていましたが、中間車の存在により、編成の自由度には一定の制約がありました。例えば、特定の編成から中間車だけを抜き取って別の短い編成を組む、といったことはできませんでした。
2700系は、2000系から「制御付き自然振り子装置」という優れた技術的伝統は受け継ぎました。しかし、編成構成においては、中間車を完全に廃止するという革新的なアプローチを取りました。これは、2000系の運用を通じて得られた「さらなる運用の効率化」という課題に対する、JR四国の回答と言えます。全車両を先頭車化することで、2000系が持っていた柔軟性をさらに一歩進め、経営資源をより効率的に活用する体制を構築したのです。


2700系は中間車なしで実現する柔軟な運用
設計思想を理解した上で、ここでは2700系が中間車なしの構成によって、実際の現場でいかに柔軟な運用を実現しているかを見ていきます。
- 多彩な組み合わせ!2700系の編成バリエーション
- 需要に応える増結時の運用スタイル
- 2700系が四国の鉄道に与えた影響
- 今後中間車が製造される可能性はあるのか
- 結論:2700系中間車の不在は最適解
多彩な組み合わせ!2700系の編成バリエーション

2700系は、3つの形式を組み合わせることで、非常に多彩な編成バリエーションを生み出します。中間車がないからこそ、これらの形式を自在に連結し、目的や需要に合わせた列車を仕立てることが可能です。
| 項目 | 2700形 (Mc) | 2750形 (Mc’) | 2800形 (Msc) |
| 主な向き | 上り(高松・岡山向き) | 下り(宿毛・徳島向き) | 下り(宿毛・徳島向き) |
| 定員 | 46名 | 52名 | 37名(グリーン12席) |
| 主要設備 | 多機能トイレ、車椅子スペース | 洋式トイレ、荷物置き場 | 半室グリーン席、多目的室 |
基本的な編成パターンは以下の通りです。
- 2両編成: 最も基本的な編成。2700形 + 2750形の組み合わせで、主に「うずしお」や「あしずり」などで見られます。
- 3両編成: グリーン車を連結した特急「南風」の基本編成(2700形 + 2700形 + 2800形など)や、普通車のみの増結編成があります。
- 4両編成: 2両編成を2本連結した形で、利用者の多い時間帯の「南風」「しまんと」などで運用されます。
- 5両編成: 3両編成と2両編成を連結した、最も長い編成。多客期の「南風」などで見られ、途中で分割されることもあります。
このように、まるでブロックを組み立てるかのように編成を構成できるのが、2700系の大きな特徴です。
需要に応える増結時の運用スタイル

2700系の真価が最も発揮されるのが、まさにこの増結や分割を伴う運用スタイルにあります。全車両が運転台と動力を持つことで、編成を一つの固定された単位としてではなく、需要に応じて自在に組み合わせられる「モジュール」として扱えるからです。
その象徴的な例として、かつては岡山駅と高知県を結ぶ特急「南風」と、高松駅と高知県を結ぶ「しまんと」の併結運転が日常的に行われていました。これは、本州からの玄関口である岡山と、四国の玄関口である高松、二つの異なる出発点からの旅客を宇多津駅で一つにまとめ、効率的に高知方面へ輸送するための非常に合理的な運用でした。例えば、岡山駅を5両編成で出発した列車が、香川県の宇多津駅で3両の「南風」と2両の「しまんと」に分割され、それぞれの目的地へ向かうといった運用がそれにあたります。
しかし、2025年3月のダイヤ改正により、この宇多津駅での複雑な分割・併合作業を伴う特徴的な運用は見直されることになりました。これは、運行の定時性向上や、運用のシンプル化を図る目的があったと考えられます。それでもなお、2700系の本質的な柔軟性が失われたわけではありません。
ゴールデンウィークやお盆、よさこい祭りなどの多客期には、2両編成の「あしずり」を4両に増結したり、3両編成の「南風」に2両を増結して5両編成で運転したりと、需要の波に合わせた輸送力調整が機動的に行われます。編成の長さを日ごと、あるいは列車ごとに最適化できるこの能力こそ、中間車を持たない2700系ならではの強みです。こうした効率的な運用思想が、まさに「生き物」のような運用スタイルと評される所以なのです。
2700系が四国の鉄道に与えた影響
2700系の導入は、JR四国の鉄道網全体にポジティブな影響を与えています。
まず、サービスレベルが大幅に向上しました。老朽化した2000系を置き換えたことで、乗り心地、静粛性が改善されただけでなく、全座席へのコンセント設置や無料Wi-Fiの提供など、現代のニーズに対応した車内設備が標準となりました。これにより、利用者の満足度は大きく向上しています。
次に、運行の安定化に貢献しています。新型車両であるため故障が少なく、予備車両の効率的な運用も可能なため、特急列車の定時運行率の維持・向上に繋がっています。
そして、特筆すべきは、第三セクターである土佐くろしお鉄道が自社で2700系を2両所有し、一体的な運用を行っている点です。これは、新型車両導入の莫大なコストを両社で分担し、広範囲でサービス水準を統一するための戦略的な協力関係を示しています。地方鉄道が持続的に近代化を進める上での、一つのモデルケースを提示したと言えるでしょう。
今後中間車が製造される可能性はあるのか
2700系の設計思想や運用実態を踏まえると、今後新たに中間車が製造される可能性は極めて低いと考えられます。
その理由は、これまで述べてきたことの繰り返しになりますが、2700系の存在意義そのものが「中間車を持たないことによる柔軟性」にあるからです。もし中間車を製造して編成に組み込んでしまうと、この最大のメリットが失われてしまいます。それは、車両の稼働率を最大化し、需要変動にきめ細かく対応するという、厳しい経営環境を乗り越えるためのJR四国の基本戦略を根底から覆すことになりかねません。
将来、四国内に新幹線が開業するなど、鉄道輸送の体系が劇的に変化し、常に高い需要が見込める固定編成の特急列車が必要とされるような状況が生まれれば可能性はゼロではないかもしれません。しかし、現在の路線網と輸送需要を前提とする限り、2700系に中間車を追加する合理的な理由は見当たらないのが実情です。
結論:2700系の中間車が不在は最適解
この記事で解説してきた内容をまとめます。JR四国の2700系に中間車が存在しないのは、決して機能の欠落ではなく、四国の地で鉄道輸送を最適化するための、極めて戦略的な選択です。
- 2700系に中間車がない最大の理由は運用の柔軟性確保
- 需要変動が激しい四国の路線網に対応するための設計
- 全車両が先頭車のため分割・併合が自由自在
- 輸送力の最適化とコスト削減を両立
- 保有車両の稼働率を最大化する資産効用の観点
- 2両1ユニットを基本とし編成を自在に組み替える
- 先行試作車2600系の空気ばね式傾斜の失敗が教訓
- 実績ある制御付き自然振り子装置を2000系から継承
- 2000系の中間車ありの編成より柔軟性をさらに向上
- 「南風」と「しまんと」の宇多津駅での分割・併合が象徴的
- 全座席コンセントなどサービスレベルが大幅に向上
- 土佐くろしお鉄道との共同所有は持続可能なモデル
- 製造コストや定員の面ではデメリットも存在する
- 今後の社会情勢の変化がない限り中間車製造の可能性は低い
- 2700系の設計はJR四国の経営戦略そのものを反映した最適解