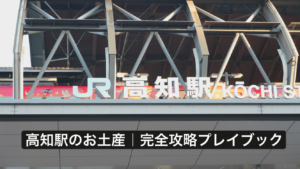こんにちは。Shikokuレールノート、運営者の「よんてつ」です。
JR四国の新型特急、2700系。かっこいいですよね!その流線形の「顔」とも言えるヘッドマークについて検索してみると、いろんな情報が出てきて迷いませんか?
「2700系のヘッドマークって、実はLEDなんでしょ?」「じゃあ、昔の2000系みたいな物理的なプレートは無いの?」「アンパンマン列車はどうなってるの?」とか、「記念ヘッドマークが付いたって聞いたけど…」なんて噂もあったり。
それに、鉄道写真を撮る方なら、撮影したら表示が真っ黒に写っちゃう「LED切れ」の問題や、そっくりな「2600系」との違い、あとは旅の記念になる「キーホルダー」情報まで、気になるポイントは結構多いと思います。
この記事では、そんな2700系のヘッドマークに関する様々な疑問について、技術的な背景から撮影のコツ、そしてよくある「誤解」まで、私がしっかり調べた最新情報(2025年11月時点)を網羅的に整理して、わかりやすく解説していこうと思います!
- 2700系ヘッドマークがLEDである技術的な理由
- 2000系との違いやアンパンマン列車の表示内容
- 撮影時の「LED切れ」を防ぐ具体的なコツ
- 「記念ヘッドマーク」に関する誤解と実際の対応
2700系ヘッドマークの技術的真実
まずは、2700系のヘッドマークが「技術的に」どうなっているのか、その基本的なところから見ていきましょう。ここを理解すると、撮影時の悩みや2000系との違い、そして「記念ヘッドマーク」の誤解もスッキリ分かってきますよ。

物理プレートではないLED表示器
いきなり結論から言ってしまうと、2700系(そして先行する2600系も)には、昔ながらの物理的なプレート、つまり金属や樹脂の「愛称板」を付け替える方式の「ヘッドマーク」は搭載されていません。
「え、じゃあ何なの?」と思いますよね。あれは、技術的にはフルカラーLEDを使った「愛称表示器」というのが正しい呼び方です。いわば、高精細な電光掲示板ですね。
じゃあ、なぜみんな今でも「ヘッドマーク」と呼ぶのか?
これは、国鉄時代から続く伝統的な「通称(呼び名)」だからです。かつて、四国でも急行列車などで見られた、あの物理的な愛称板(プレート)の印象があまりにも強いため、利用者の間では、車両の「顔」のあの位置にある愛称表示部分全体を、習慣的に「ヘッドマーク」と呼び続けているんですね。
2700系の前に四国で活躍した特急車両、例えばキハ181系、キハ185系、そして2000系気動車の多くは、物理プレートではなく「電動幕式(ロールサイン)」を採用していました。
しかし、私たちはその「幕式」の表示器のことも、通称として「ヘッドマーク」と呼んでいましたよね。
つまり、技術が「物理プレート」から「幕式」へ、そして「LED式」へと進化しても、多くの人にとって車両の先頭で愛称を示すあの場所は、変わらず「ヘッドマーク」なんです。
2000系との決定的な違い

長年、土讃線などで活躍した2000系気動車は、本当に名車でした。そして、その顔にはいつも誇らしげに、デザイン性の高い愛称表示がされていましたよね。
「電動幕式(ロールサイン)」で、あらかじめ「南風」「しまんと」「あしずり」といった複数の愛称ロゴが印刷された幕(ブラインド)を内蔵し、運用に合わせてモーターで回転・表示させる仕組みです。
あの幕式ならではの、内側から照らされた鮮やかなデザインや、アナログな機構感が大好きだった、という方も多いんじゃないでしょうか。
それに対して、2700系は「フルカラーLED愛称表示器」という完全なデジタル方式になりました。幕を回転させるのではなく、電子スクリーンにドットで文字やデザインを描画します。この「アナログの幕式」から「デジタルのLED式」への移行は、単なる見た目の変化ではなく、鉄道の運用上、非常に大きなメリットをもたらしました。
2700系(デジタル式)のメリット
- 運用の超柔軟化: 物理的な交換作業が一切不要に。プログラム(仕業データ)を切り替えるだけで、「南風」「しまんと」「うずしお」など、異なる愛称表示を瞬時に変更できます。
- 複雑な運用への対応力: 2700系導入時は、宇多津駅や多度津駅で複数の列車を分割・併合する複雑な運用が日常的に行われていました。LED表示器は、そうした運用に柔軟に対応するために不可欠な装備でした。
- 表現力の向上: LEDならではの高輝度な発光で、昼夜問わず視認性が高いです。さらに、ドットマトリクス(点の集まり)によるデジタル描画も可能です。(ただし、後述するアンパンマン列車ではこの機能は使われていません)
もちろん、2000系のあの「味」が失われたのは少し寂しい気もしますが、2700系の表示器は、現代の効率的な列車運用に最適化された「進化したヘッドマーク」と言えるんですね。
撮影時に発生するLED切れ問題

2700系を撮影しようとカメラを構えた時、特に鉄道写真ファンの方が直面するのが、あの「LED切れ」問題です。
「バッチリ撮れた!」と思ったのに、後でデータを見返したら、肝心の愛称表示器がシマシマの横スジだらけになったり、最悪の場合、真っ黒に何も写っていなかったり…。これ、結構ショックですよね。
なぜこんなことが起こるかというと、LED表示器というのは、人間の目には常時点灯しているように見えても、実はものすごい速さで点滅(リフレッシュ)を繰り返して表示を維持しているからなんです。
この点滅の周期(リフレッシュレート)と、カメラのシャッタースピードがうまく同期しない(ズレる)と、LEDが「消えている瞬間」をカメラが捉えてしまい、結果として「LED切れ」や「フリッカー現象(ちらつき)」として写真に写ってしまうわけです。(※この問題は、後述するアンパンマン列車仕様の2600系・2700系では発生しません)
撮影対策はシャッター速度にあり

じゃあ、どうすればあのLED表示をキレイに写せるのか?(※ノーマル仕様の2700系・8600系や、5000系・7200系の行き先表示などJR四国車両全般の対策です)
対策はシンプルで、シャッタースピードをLEDの点滅周期よりも遅くすることです。
私の経験や多くの鉄道写真ファンの方々の報告によると、JR四国の車両(2700系含む)の場合、シャッタースピードをだいたい「1/100秒」以下(1/80秒や1/60秒など)に設定すると、LED切れを起こさずにキレイに写る可能性が非常に高いようです。
※これはあくまで目安です。1/125秒でも写る場合があるかもしれませんが、安全マージンを見るなら1/100秒以下が確実かなと思います。撮影時の明るさや状況によっても変わる可能性はあります。
ただ、この「1/100秒以下」というのが、鉄道写真、特に走行中の列車を撮る上での大きなジレンマになります。
 よんてつ
よんてつ私は可変NDフィルターを使うことが多いです。
走行写真でのジレンマ:被写体ブレとの戦い
シャッタースピードを1/100秒や1/60秒まで遅くすると、今度は高速で走る列車自体がブレてしまう、いわゆる「被写体ブレ」のリスクが急激に高まります。
相反する二つの要求
列車をビシッと止めたい(速いシャッタースピード、例:1/500秒以上)という要求と、ヘッドマークのLEDをキレイに写したい(遅いシャッタースピード、例:1/100秒以下)という要求が、真っ向から対立してしまうんです。
具体的な撮影テクニック
このジレンマを解決するには、いくつかのテクニックが必要になります。
- 流し撮り: カメラを列車の動きに合わせて振りながら、遅いシャッタースピードで撮影する高等テクニックです。背景だけが流れ、列車は止まって写るため、LED切れと被写体ブレを両立できますが、高い技術と練習が必要です。
- ISO感度と絞りの調整: シャッタースピードを遅くする分、写真が明るくなりすぎないよう、ISO感度を最低(例:ISO100)にし、絞り(F値)をF8やF11などに絞り込む調整が基本になります。
- 停車中を狙う: 最も確実で簡単なのは、駅に停車しているところを撮影することです。これなら被写体ブレの心配がないため、安心してシャッタースピードを1/100秒以下に設定できます。
走行写真を狙う場合は、シャッタースピード、ISO感度、絞り、そして天候(明るさ)のバランスを高度に調整する必要がある、と覚えておいてください。撮影の際は、周りの安全に十分配慮してくださいね。
2600系との表示器の共通点

JR四国の特急車両には、2700系と本当によく似た顔の「2600系」がいますよね。主に高松~徳島間の特急「うずしお」で活躍していました。
以前は、2700系とこの2600系は同一のフルカラーLED愛称表示器を搭載しており、「外観も表示器もそっくりな兄弟車両」という認識で間違いありませんでした。そのため、2600系撮影時も2700系と全く同じ「LED切れ」対策(シャッタースピード1/100秒以下)が必要でした。
しかし、その状況は大きく変わりました。

全編成がアンパンマン列車へ
ご指摘の通り、2025年10月25日より、2600系は全編成が「高徳線 うずしおアンパンマン列車」としての運行にリニューアルされました。
これに伴い、2600系の前面は、後述する2700系アンパンマン列車と同様に、LED表示器の部分も含めてアンパンマンのキャラクターが描かれたラッピングシートで完全に覆われるデザインに変更されました。
したがって、現在(2025年11月時点)では、2600系のLED愛称表示器を外から見ることはできなくなりました。もちろん、撮影時にLED切れを心配する必要も(物理的に)なくなった、ということになりますね。これは非常に大きな変化です。
表示される愛称の種類一覧
2700系はJR四国の現在の主力気動車特急として、四国内の主要な電化されていない路線(非電化路線)で幅広く活躍しています。(※アンパンマン仕様ではない、ノーマル塗装の車両の話です)
そのため、愛称表示器にも複数の列車名(ロゴ)が表示されます。現在、定期運用で主に見られるのは、以下のような愛称ですね。
| 表示愛称 | 読み | 主な運用区間 |
|---|---|---|
| 南風 | なんぷう | 岡山~高知 |
| しまんと | しまんと | 高松~高知・中村 |
| うずしお | うずしお | 岡山・高松~徳島 |
| 宇和海 | うわかい | 松山~宇和島 |
| あしずり | あしずり | 高知~中村・宿毛 |
南風・しまんとの併結運転は終了
以前のJR四国では、岡山発着の「南風」と高松発着の「しまんと」が、香川県の宇多津駅(または多度津駅)で連結・切り離しを行う「併結運転」が日常的に行われていました。2700系のLED表示器は、まさにこうした複雑な運用を支える重要な機能でした。
しかし、2025年3月15日のダイヤ改正をもって、この「南風」と「しまんと」(「うずしお」も)の併結運転は終了となりました。
現在(2025年11月時点)のダイヤでは、「南風」は岡山~高知間、「しまんと」は高松~高知・中村間を、それぞれ独立した列車として運転されています。快速「サンポート」南風リレー号による乗り換えが必要になったケースもありますが、運用としてはシンプルになりましたね。
2700系は、そうした過去の複雑な運用から現在の独立運用まで、ダイヤ改正にも柔軟に対応できる車両だ、ということですね。
2700系ヘッドマークの疑問を解消
さて、ここからは技術的な話から一歩進んで、皆さんが「2700系 ヘッドマーク」と検索した時に、特に気になっているであろう「アンパンマン列車」や、鉄道ファンならではの「記念ヘッドマーク」といった、具体的な疑問についてお答えしていきますね。
アンパンマン列車の特別表示

2700系のヘッドマークを語る上で、「アンパンマン列車」は欠かせない要素です。特急「南風」の一部(土讃線アンパンマン列車)は、2020年から従来の2000系に代わり、この2700系が使われています。
LED表示器はラッピングで隠されています
2700系の土讃線アンパンマン列車(「あかいアンパンマン列車」と「きいろいアンパンマン列車」の2編成)は、前面のLED愛称表示器の部分も含めて、アンパンマンやばいきんまんの顔が描かれたラッピングシートで完全に覆われています。
つまり、あの部分はLED表示器として機能しておらず、光ったり、愛称が表示されたりすることはありません。デザイン(顔)の一部として固定化されている、というのが正しい状態です。(出典:JR四国 観光列車<アンパンマン列車 土讃線>)
2000系時代は物理的なアンパンマンのヘッドマークを装着していましたが、2700系では車体デザインと一体化したラッピング表現になった、ということですね。これは先に述べた2600系「うずしおアンパンマン列車」とも共通の仕様です。
記念ヘッドマークという大きな誤解
さて、ここが今回の記事で(アンパンマン列車と並んで)非常に重要なポイントです。
「2700系に、瀬戸大橋線開業35周年とかの『記念ヘッドマーク』が付いた」という情報を見聞きしたことはありませんか? こうした「記念〇〇」系の情報を探している鉄道ファンの方は結構多いようです。
実はこれ、多くの方が陥っている、ある「誤解」に基づいている可能性が非常に高いんです。
結論から言うと、2700系は(私の知る限り)前面に物理的な「記念ヘッドマーク(プレート)」を取り付けたことはありません。
なぜか?それは「構造的な理由」です。2700系の前面デザインをよく見てもらうとわかりますが、愛称表示器(LEDパネル)が車体にがっちりとはめ込まれています。2000系や、本州の国鉄型車両にあったような、物理的なプレートを装着するための「台座(ブラケット)」や「ステー(留め具)」が、そもそも存在しない構造になっているんです。
周年記念は側面ラッピングが正解
では、なぜ「2700系に記念ヘッドマークが付いた」という誤解が広まったんでしょうか。
それは、例えば2023年の「瀬戸大橋線 開業35周年」記念イベントの時の情報が原因だと思われます。
この時、JR四国は複数の車両に記念装飾を施しました。ここで、車両によって対応に決定的な違いがあったんです。
記念装飾の決定的な違い(瀬戸大橋線35周年の例)
- 5000系「マリンライナー」: こちらは車体前面にヘッドマークを取り付ける「台座」があるため、専用デザインの物理的な「記念ヘッドマーク」が取り付けられました。
- 2700系(や8000系, 8600系): こちらは前面に「台座」がない構造のため、ヘッドマークではなく、「車体側面」に記念ロゴのステッカー(ラッピング)が貼り付けられました。
この事実を知らずに、ニュース記事などで「瀬戸大橋線35周年記念」と「2700系」という言葉が同時に目に入ると、「2700系にもあのヘッドマークが付いたんだ!」と誤解してしまうわけです。
誤解が生まれた背景:ニュース記事の読み違え
ニュース記事の見出しや本文では、これら(5000系へのHM装着と、2700系への側面ラッピング)が「記念装飾」として一括りで紹介されることがよくあります。そのため、記事をサッと読んだだけだと、「ヘッドマークは5000系だけ」「2700系は側面ロゴのみ」という重要な違いを見落としてしまい、混同が起きてしまった…というのが真相かなと、私は推測しています。
ですので、2700系のイベント装飾は、基本的に「側面ラッピング(ステッカー)」で対応する、と覚えておくのが、現時点での正解ですね。(将来的にLED表示器に記念ロゴデータをプログラムして表示する可能性はゼロではありませんが、今のところ主な対応は側面です)
キーホルダーなどグッズは購入できるのか?
「2700系に乗った記念に、ヘッドマークのキーホルダーが欲しい!」と思う方もいらっしゃるようです。わかります、その気持ち。
定番商品としては販売されていない可能性
結論から言うと、2700系がLEDで表示する「南風」や「しまんと」といった伝統的な愛称ロゴをデザインしたキーホルダーは、現在(2025年時点)、JR四国の主要駅の売店(Kiosk)や通販サイトで「定番商品」としては販売されていないようです。
昔は国鉄時代や2000系時代に、そうしたグッズが色々とあった記憶があるのですが、現在はラインナップから外れているか、あるいは非常に見つけにくい状況になっているのだと思われます。
代替となる記念グッズは?
では、ヘッドマーク(愛称ロゴ)以外の記念グッズはないのでしょうか?
もちろん、そんなことはありません。キーホルダーという形にこだわりすぎなければ、2700系に関連する記念グッズは他にもあります。
- 車両デザインのグッズ: 2700系の車両イラストが描かれた「クリアファイル」や「タオル」、「靴下(キッズサイズ)」などは、比較的見つけやすい記念グッズかなと思います。
- アンパンマン列車グッズ: アンパンマン列車に乗車した場合、高知駅の「アンパンマン列車ひろば」などでは、限定のオリジナルグッズが販売されています。こちらの方が記念品としては探しやすいかもしれませんね。
「ヘッドマークキーホルダー」という一点狙いだと見つからない可能性が高いので、「2700系に乗った記念」として、少し視野を広げて探してみるのが良さそうです。
総括:2700系ヘッドマークの全知識

今回は、JR四国の主力「2700系」のヘッドマークについて、その技術的な実体から、撮影のコツ、そして重大な誤解まで、最新の情報(2025年11月時点)で詳しく掘り下げてみました。
最後に、この記事の最も重要なポイントをもう一度おさらいしておきましょう。
2700系ヘッドマークのまとめ
- 実体は物理プレートではなく「フルカラーLED愛称表示器」というデジタルな装置である。
- (ノーマル仕様の車両は)撮影時にシャッタースピード「1/100秒以下」を目安にしないと「LED切れ」を起こしやすい。
- 「アンパンマン列車」(2700系・2600系共)は、LED表示器部分がラッピングで隠されており、表示は見えない。
- 構造上、物理的な「記念ヘッドマーク」は取り付けられず、イベント時は「側面ラッピング」で対応するのが基本である。
- 「南風」と「しまんと」「うずしお」の併結運転は2025年3月で終了し、現在は独立運転となっている。
- 愛称ロゴの「キーホルダー」は、定番商品としては販売されていない可能性が高い。
2000系が誇った物理プレートの「アナログな格好良さ」から、2700系の「デジタルな機能美」へ。そしてアンパンマン列車ではその表示機能ごと「ラッピングデザイン」に組み込むという、新しい表現方法へ。車両の「顔」に注目するだけでも、時代ごとの設計思想や、ダイヤ改正による運用の変化が見えてきて面白いですよね。
この記事が、あなたの「2700系 ヘッドマーク」に関する疑問解消のヒントになれば、そして2700系の旅や撮影がもっと楽しくなれば、私にとって何より嬉しいです!