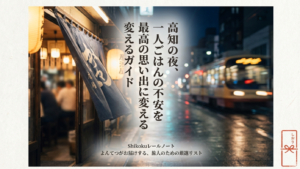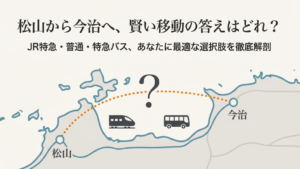JR四国の黒字路線はどの路線?と興味をお持ちのあなたは、どの路線が利益を上げているのか、そしてなぜ鉄道事業が厳しいと言われる中で会社全体としては黒字なのか、その理由を知りたいと思っているのではないでしょうか。
実際、2024年度の黒字路線はわずか一つですが、JR四国グループ全体では黒字を達成しています。この記事では、路線ごとの収支比較(黒字 vs 赤字)から、JR四国の黒字転換理由の核心である経営安定基金の存在、他のJR各社との黒字路線比較まで、多角的に解説します。さらに、特急列車の収益構造とはどのようなものか、観光列車がもたらす収益効果、黒字化に貢献したキャンペーン事例としての駅ビル開発、沿線地域の経済効果と連携策、そして利用者数が多い主要駅ランキングの背景にある実情にも迫ります。
今後の黒字維持に向けた施策と合わせて、JR四国の経営の全体像を深く理解できる内容となっています。
この記事を読むことで、以下の点について理解が深まります。
- JR四国で唯一黒字を達成した路線名とその理由
- ほとんどの路線が赤字なのに、会社全体が黒字となる経営の仕組み
- 観光列車や駅ビル開発といった鉄道以外の事業が収益を支える戦略
- 厳しい経営環境の中で進められているコスト削減や地域連携の取り組み
JR四国 黒字路線の状況を分析
- 2024年度の黒字路線は瀬戸大橋線のみ
- 路線ごとの収支比較(黒字 vs 赤字)
- 他のJR各社との黒字路線比較
- 利用者数が多い主要駅ランキング
- 特急列車の収益構造とは
2024年度の黒字路線は瀬戸大橋線のみ

JR四国が管轄する全18区間のうち、2024年度(2025年3月期)の決算で黒字を達成したのは、本四備讃線(ほんしびさんせん)、通称「瀬戸大橋線」の児島駅から宇多津駅の間のみです。これは、2025年度においても同様の傾向が続くと考えられます。
その理由は、この路線が持つ特殊な役割にあります。瀬戸大橋線は、四国と本州を結ぶ唯一の鉄道ルートであり、多くの旅客が利用する山陽新幹線への乗り換え拠点である岡山駅と四国をつなぐ大動脈です。そのため、ビジネスや観光の需要が非常に高く、安定した収益を確保しています。
具体的には、2023年度のデータで営業収益が約33億円に対し、営業費用は約24億円に留まり、約9億円もの営業利益を生み出しました。100円の収入を得るためにかかる費用を示す「営業係数」は73円と、JR四国の中では突出して高い収益性を誇ります。このように、瀬戸大橋線の黒字は、その代替のきかない重要な役割によって支えられているのです。
路線ごとの収支比較(黒字 vs 赤字)

JR四国の経営状況を理解する上で、路線ごとの収支の大きな差を知ることが大切です。前述の通り、唯一黒字の瀬戸大橋線がある一方で、多くの路線は深刻な赤字に直面しています。
特に厳しい状況にあるのは、山間部や沿岸部を走る地方路線です。例えば、2023年度のデータを見ると、予土線の北宇和島―若井間の営業係数は1,329円、牟岐線の阿南―阿波海南間は1,055円でした。これは、100円の運賃収入を得るために、それぞれ約1,330円、約1,050円もの経費がかかっていることを意味します。人口減少やマイカー利用の普及が、これらの路線の経営を直撃しているのです。
一方で、高松や松山といった県庁所在地を結ぶ幹線の一部は、赤字ではあるものの比較的状況は良好です。以下の表は、主要な区間の収支状況を比較したものです。この収支の格差こそ、JR四国が抱える構造的な課題を浮き彫りにしています。
| 線区 | 営業収益 (百万円) | 営業損益 (百万円) | 営業係数 (円) | 収支状況 |
| 本四備讃線 (児島~宇多津) | 3,314 | 901 | 73 | 唯一の黒字 |
| 予讃線 (多度津~観音寺) | 1,400 | ▲162 | 112 | 比較的損失が少ない赤字 |
| 予讃線 (高松~多度津) | 4,071 | ▲1,050 | 126 | 比較的損失が少ない赤字 |
| 土讃線 (琴平~高知) | 2,509 | ▲2,262 | 190 | 大きな赤字 |
| 予讃(海線) (向井原~伊予大洲) | 213 | ▲612 | 387 | 深刻な赤字 |
| 牟岐線 (阿南~阿波海南) | 88 | ▲845 | 1,055 | 極めて深刻な赤字 |
| 予土線 (北宇和島~若井) | 81 | ▲992 | 1,329 | 極めて深刻な赤字 |
| ※出典: JR四国 2023年度線区別収支状況 | ||||
他のJR各社との黒字路線比較
JR四国の経営状況は、他のJR各社と比較すると、その特殊性がより明確になります。特に、同じく国鉄分割民営化の際に発足したJR北海道、JR九州とは「三島会社」と称され、当初から厳しい経営が見込まれていました。
これらの会社は、経営基盤が脆弱であるため、国から「経営安定基金」という財政支援を受けて発足しました。JR東日本やJR東海のように、東海道新幹線や大都市圏の通勤路線といった収益の柱となる路線を持たないためです。JR九州は近年、鉄道事業の黒字化や不動産事業の成功で経営を軌道に乗せつつありますが、JR北海道とJR四国は依然として鉄道事業単体での黒字化には至っていません。
本州のJR3社(東日本、東海、西日本)は、多くの黒字路線を抱え、特に大都市圏の通勤輸送や新幹線事業で莫大な利益を上げています。これに対して、JR四国で黒字路線が瀬戸大橋線のみという現実は、四国地域の人口規模や経済基盤を考えると、ある意味で構造的な問題と言えます。このように、他のJR各社、特に本州の会社とは収益構造の根本が大きく異なっているのです。

利用者数が多い主要駅ランキング
JR四国の公式な駅別利用者数ランキングは毎年詳細に公表されているわけではありませんが、路線の利用状況から、利用者数が多い主要駅を推測することは可能です。
最も利用者数が多いのは、香川県の玄関口である高松駅と考えられます。高松駅は、県庁所在地であるだけでなく、四国の各方面へ向かう特急列車や、本州へ渡る瀬戸大橋線の快速マリンライナーの始発駅であり、四国最大のターミナル駅として機能しています。2024年3月には駅ビル「TAKAMATSU ORNE」が開業し、さらなる賑わいを見せています。
次いで、愛媛県の松山駅、高知県の高知駅、徳島県の徳島駅といった各県の中心駅が続きます。これらの駅は、通勤・通学利用者に加え、ビジネスや観光の拠点として多くの人々が利用します。特に松山駅周辺では、鉄道の高架化事業と連動した大規模なまちづくりが進行中で、将来的な利用者の増加が期待されます。
このように、利用者が多い駅は県庁所在地に集中しており、これらの駅を含む幹線区間が、赤字ではありながらもJR四国の鉄道事業を支える重要な役割を担っています。
特急列車の収益構造とは

JR四国の鉄道事業において、特急列車は収益の根幹をなす非常に重要な存在です。普通列車や快速列車だけでは、運賃収入だけとなり収益性が低くなりがちですが、特急列車は運賃に加えて特急料金が得られるため、収益性が高くなります。
四国内の主要都市間(高松、松山、徳島、高知)は、高速道路網が整備されているものの、鉄道による定時性や快適性を求めるビジネス客や観光客の需要が根強くあります。「しおかぜ」「いしづち」「うずしお」「南風」といった特急列車ネットワークが、これらの都市間輸送を担い、JR四国の運輸収入を支える大黒柱となっているのです。
一方で、収益性をさらに高めるためのコスト削減も進められています。その一例が、特急列車の一部区間でのワンマン運転です。例えば、特急「宇和海」の八幡浜―宇和島間では、運転士のみが乗務するワンマン運転が実施されています。これにより人件費を削減できますが、安全確保のための設備投資や、緊急時対応の課題といった側面も考慮する必要があります。このように、特急列車は高い収益性を確保しつつも、厳しい経営環境を反映した合理化が進められているのが実情です。
JR四国 黒字路線 2期連続黒字達成を支える経営戦略
- JR四国の黒字転換理由と経営安定基金
- 観光列車がもたらす収益効果
- 黒字化に貢献したキャンペーン事例
- 沿線地域の経済効果と連携策
- 今後の黒字維持に向けた施策
JR四国の黒字転換理由と経営安定基金

ほとんどの路線が赤字であるにもかかわらず、JR四国グループ全体が最終黒字を達成している最大の理由は、鉄道事業以外の収益、特に「経営安定基金」の存在にあります。
経営安定基金とは、1987年の国鉄分割民営化の際に、JR四国のような赤字経営が見込まれた会社に対して国が造成した基金です。当初、この基金を運用して得られる利益(運用益)で、鉄道事業の赤字を補う計画でした。しかし、その後の低金利により、計画通りの運用益を確保することが困難になりました。
この事態を受け、国は追加の支援策を講じています。現在では、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構(JRTT)を通じて、無利子の貸付や助成金という形で強力な財政支援が行われています。この経営安定基金から生じる営業外収益が計上されており、鉄道事業の営業損失の大部分を埋め合わせ、会社全体の経常利益を黒字に押し上げる決定的な要因となっています。
つまり、JR四国の黒字は、鉄道事業の儲けによるものではなく、国の支援を背景とした財務的な仕組みによって成り立っているのが実態です。
観光列車がもたらす収益効果

鉄道事業の赤字を少しでも圧縮し、地域の魅力を発信するためにJR四国が力を入れているのが、観光列車です。これらの列車は、単なる移動手段ではなく、乗ること自体が目的となる「コト消費」を提供し、高い収益効果を生み出しています。
代表的なものに、以下の「ものがたり列車」シリーズがあります。
- 伊予灘ものがたり(予讃線): 海沿いの絶景を眺めながら、地元の食材を活かした豪華な食事を楽しめます。2022年には車両がリニューアルされ、さらに人気が高まっています。
- 四国まんなか千年ものがたり(土讃線): 秘境と呼ばれる大歩危・小歩危の渓谷美を車窓から満喫できます。
- 志国土佐 時代の夜明けのものがたり(土讃線): 幕末の志士たちに思いを馳せる、歴史と食をテーマにした列車です。
これらの観光列車は、通常の運賃・特急料金に加えて、食事代などを含んだ旅行商品として販売されるため、客単価が非常に高くなります。普段は利用者が少なく採算が取れない景勝地を走る路線であっても、全国から観光客を呼び込むことで新たな収益源とすることが可能です。この戦略は、鉄道の新たな価値を創造し、四国全体の観光振興にも大きく貢献しています。
黒字化に貢献したキャンペーン事例

JR四国がグループ全体の黒字化を達成する上で、鉄道事業の赤字を補う非鉄道事業の成長が不可欠です。その中でも、近年大きな成功を収めているのが、駅という一等地の資産を最大限に活用した不動産開発です。これを広義の「キャンペーン」と捉えることができます。
TAKAMATSU ORNE(タカマツ オルネ)
2024年3月に高松駅に開業した新しい駅ビルです。ファッション、雑貨、グルメなど多彩なテナントが集結し、開業初年度の売上は計画を上回る約54億円に達しました。これは、単に駅の利便性を高めるだけでなく、街の新たなランドマークとして人を呼び込み、大きな収益を生み出すことに成功した事例です。
JR松山駅だんだん通り
2024年9月に全面開業した松山駅高架下の商業施設です。飲食店や物販店が軒を連ね、地域住民や観光客の新たな憩いの場となっています。鉄道の高架化事業によって生まれた空間を有効活用し、収益源に変えた好例と言えます。
これらの駅ビルや商業施設開発は、鉄道利用客だけでなく、地域に住む人々をターゲットにすることで安定した収益が見込めます。鉄道事業との相乗効果も期待でき、グループ全体の黒字化に大きく貢献する重要な戦略となっています。
沿線地域の経済効果と連携策

JR四国は、厳しい経営環境を乗り切るため、沿線の自治体や他の交通事業者との連携を積極的に進めています。これにより、地域交通全体の利便性を向上させ、路線の維持と地域経済の活性化を図っています。
牟岐線モデル(バスとの共同経営)
特に注目されるのが、徳島県南部を走る牟岐線での取り組みです。利用者が極端に少ない阿南以南の区間で、並行してバスを運行する徳島バスと「共同経営」を開始しました。これは、利用者がJRの乗車券や定期券で徳島バスにも乗車できるという画期的な仕組みです。
この連携により、鉄道の運行本数を増やすことなく、利用者にとっては実質的な便数が増え、利便性が大幅に向上しました。バス会社にとってもJRからの利用客を取り込めるメリットがあり、持続可能な地域交通網を模索する上での先進的なモデルケースとして全国から注目されています。
予土線の利用促進
日本最後の清流と呼ばれる四万十川沿いを走る予土線では、「海洋堂ホビートレイン」などユニークな車両を「予土線3兄弟」としてブランド化し、観光客誘致に力を入れています。沿線自治体も利用促進協議会を立ち上げ、イベント開催などでJR四国を支援しており、官民一体となった路線の維持・活性化が図られています。
今後の黒字維持に向けた施策

JR四国は、2031年度までに国の支援に頼らない「経営自立」を達成するという高い目標を掲げています。この目標に向け、「長期経営ビジョン2030」のもと、鉄道事業の合理化と非鉄道事業の拡大という二つの柱で施策を進めています。
第1の柱:鉄道事業の合理化
コスト削減が最優先課題であり、徹底した省力化・省人化が進められます。
- ワンマン運転の拡大: 普通列車に加え、特急列車でもワンマン運転区間を拡大し、人件費を抑制します。
- 駅業務の自動化: オペレーターが遠隔で対応する「みどりの券売機プラス」の導入を進め、みどりの窓口の営業時間を短縮するなど、駅係員の配置を効率化します。
- インフラの近代化: レールや枕木の交換、車両工場の設備更新など、将来のメンテナンスコストを削減するための投資を計画的に行います。
第2の柱:非鉄道事業の積極的な拡大
鉄道事業の赤字をカバーし、グループ全体の収益の柱とするため、関連事業への投資を加速させます。
- 不動産事業: 高松駅や松山駅での成功をモデルに、他の駅周辺でも開発を進めます。
- ホテル事業: 「JRクレメントイン」ブランドを中心に、四国内外への新規出店を検討しています。
- M&A(企業の合併・買収): 建設コンサルタント会社や医療機器会社を買収するなど、鉄道とは異なる分野の事業を取り込み、新たな収益源を確保します。
これらの施策を通じて、厳しい経営環境の中でも持続可能な企業体質を構築していく計画です。
JR四国 黒字路線の未来を考察
この記事で解説してきた内容を踏まえ、JR四国 黒字路線 2023年度の状況と今後の展望について、重要なポイントを以下にまとめます。
- JR四国で唯一の黒字路線は本州と四国を結ぶ本四備讃線(瀬戸大橋線)
- 瀬戸大橋線の黒字は山陽新幹線への接続という代替不可能な役割によるもの
- 予土線や牟岐線など多くの地方路線は深刻な赤字構造にある
- 100円の収入に1,000円以上を要する路線も存在する
- 鉄道事業全体では年間100億円を超える巨額の営業損失を計上
- 会社全体が黒字なのは国の支援を背景とした経営安定基金の運用益が理由
- グループの最終黒字は鉄道事業の収益力ではなく財務的な仕組みで成り立っている
- 鉄道事業の赤字を補うため非鉄道事業の多角化を積極的に推進
- 高松駅の「TAKAMATSU ORNE」など駅ビル開発が新たな収益の柱に
- 「ものがたり列車」などの観光列車は赤字路線を価値ある観光資源に変える戦略
- 特急列車は運賃と特急料金で収益を支えるがコスト削減も同時に進行
- 牟岐線でのバスとの共同経営は地域交通維持の新たなモデルケース
- 今後の施策はワンマン運転拡大などの徹底した合理化が中心
- ホテル事業やM&Aによる事業ポートフォリオの多角化も加速
- 最終目標は国の支援に頼らない「経営自立」の達成