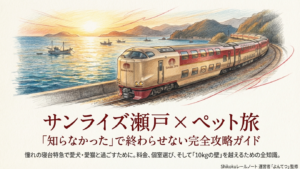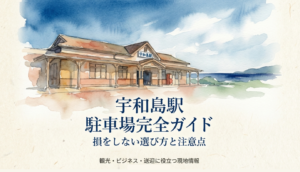徳島県の玄関口である徳島駅を訪れた際、徳島駅 自動改札機がないことに驚く方も多いのではないでしょうか。全国の県庁所在地駅では珍しくなった、係員による有人改札の様子を見ると、「徳島駅の改札スタイルとは?」や「ICカードは使えるのか?」といった疑問が浮かぶかもしれません。
この記事では、徳島駅に自動改札機がない理由や、その自動改札機未設置の背景について、四国の他駅との比較を交えながら深く掘り下げます。また、徳島駅でのきっぷの通し方、旅行者が注意すべきポイント、利用者の反応や口コミ、そして将来的に自動改札機は導入される?といった、皆さんが知りたい情報を網羅的に解説していきます。
- 徳島駅の改札がなぜ有人方式なのかが分かる
- ICカードが使えない理由と背景を理解できる
- 四国の他の主要駅とのインフラの違いが明確になる
- 旅行や出張で訪問する際の具体的な注意点が把握できる
徳島駅 自動改札機の現状と未設置の理由
- 徳島駅の改札スタイルとは
- 係員による有人改札の様子
- 徳島駅でのきっぷの通し方
- ICカードは使えるのか?
- 徳島駅に自動改札機がない理由
徳島駅の改札スタイルとは

徳島駅の改札は、現在も「有人改札方式」を採用しています。これは、自動改札機が設置されておらず、駅係員が乗客一人ひとりの乗車券を目視で確認し、入鋏(スタンプを押すこと)や回収を行う伝統的なスタイルです。
徳島駅の改札口は1箇所のみで、ラッチ(仕切り)が並んでいますが、そこを通過する機械はありません。都市部の駅で当たり前となっている、ICカードをタッチしたり、切符を機械に投入したりする風景とは異なり、ここでは人と人とのやり取りが改札業務の中心となっています。
この方式は、2025年春にJR鳥取駅が自動改札機を導入したことにより、全国の県庁所在地のJR中心駅としては徳島駅が唯一の存在となりました。JR四国管内で高松駅に次いで第2位の乗車人員(2023年度で1日平均6,502人)を誇る駅としては、非常に特異な状況と言えます。
係員による有人改札の様子

徳島駅の改札口では、通勤・通学ラッシュの時間帯も含め、常に駅係員が配置されています。乗客は改札を通過する際、駅係員に「きっぷ(乗車券)」や「定期券」をはっきりと提示する必要があります。
駅係員は、乗車券の有効期限や区間、特急券の要否などを瞬時に確認します。そして、これから乗車する人には「入鋏印」と呼ばれるスタンプを押し、降車した人からは乗車券を回収します。この一連の流れが、非常にスムーズに行われているのが特徴です。
自動改札機に慣れていると、一見すると非効率に感じるかもしれませんが、熟練した駅係員による対応は迅速です。また、乗り換え案内や道順の質問などにも柔軟に対応できるという点は、有人改札ならではの利点とも考えられます。
徳島駅でのきっぷの通し方
徳島駅には自動改札機が存在しないため、きっぷを機械に通す(投入する)というプロセス自体がありません。
乗車時(改札を通る)
まず、券売機や「みどりの窓口」で目的の駅までの紙のきっぷ(乗車券)を購入します。改札口に着いたら、そのきっぷを駅係員にはっきりと見えるように提示してください。駅係員が乗車券を確認し、日付や入鋏印(スタンプ)を押して返してくれます。そのきっぷを受け取って、改札内に入場します。
降車時(改札を出る)
列車を降りて改札口に向かい、持っているきっぷを駅係員に渡します。駅係員が区間や料金を確認し、きっぷを回収します。これで改札を出ることができます。
定期券の場合も同様で、駅係員に券面を提示して通過します。自動改札機のように定期券を投入したりタッチしたりする必要はありません。

ICカードは使えるのか?
徳島駅では、自動改札機が設置されていないため、Suica(スイカ)やICOCA(イコカ)、PASMO(パスモ)といった全国相互利用可能な交通系ICカードは一切利用できません。
これは、改札の通過だけでなく、券売機でのICカードチャージ(入金)や、ICカードを使用した乗車券の購入にも対応していないことを意味します。徳島駅を利用する際は、必ず現金で紙のきっぷを購入する必要があります。
都市部からの旅行者や出張者が特に戸惑いやすいポイントであり、ICカードが使える前提で駅に来てしまうと、きっぷを買い直す手間が発生するため、事前の準備が大切です。徳島県内のJR線は、徳島駅を含め、全線でICカードが利用不可となっています。

徳島駅に自動改札機がない理由

徳島駅に自動改札機が設置されていない直接的な理由は、交通系ICカードのシステムが導入されていないためです。自動改札機は、ICカードや磁気化されたきっぷを読み取るシステムと一体で機能するため、単に機械を設置すればよいというものではありません。
では、なぜそのICカードシステムが導入されないのでしょうか。最も大きな要因は、導入と維持にかかる莫大なコストです。
自動改札機の設置には、機械本体の費用だけでなく、各駅のシステム改修、サーバーの管理、他の鉄道会社との精算システムの連携など、多額の初期投資と継続的なランニングコストが発生します。
前述の通り、事業者であるJR四国は、鉄道事業が恒常的に赤字であり、経営安定基金の運用益で全体の黒字を維持しているという厳しい財務状況にあります。そのため、限られた経営資源は、乗客の安全を守るためのインフラ(橋梁、トンネル、信号設備)の維持・更新や、法的に必要な耐震補強などに最優先で振り分けられます。
利便性向上に資する自動改札機の導入は、安全運行に直結する投資に比べて優先順位が低くならざるを得ないのが実情です。

徳島駅への自動改札機の導入と将来展望

- 自動改札機未設置の背景
- 四国の他駅との比較
- 利用者の反応や口コミ
- 旅行者が注意すべきポイント
- 将来的に自動改札機は導入される?
- 徳島駅への自動改札機設置の課題と今後
自動改札機未設置の背景
徳島駅に自動改札機が設置されていない背景には、単なるコスト問題だけでなく、複数の要因が複雑に絡み合っています。
1. 徳島県特有の交通文化
徳島県は、全国的に見ても極めて「クルマ社会」が発達している地域です。県民の日常の移動手段は自家用車が圧倒的なシェアを占めており、鉄道への依存度が相対的に低いという特徴があります。また、京阪神など都市部への移動も、自家用車や高速バスが非常に強力な競合相手となっています。
歴史的に見ても、徳島県は全国で唯一、JRの路線が一度も電化されたことのない県であり、鉄道はディーゼルカー(気動車)による運行が続いています。こうした背景から、鉄道インフラの近代化に対する社会的な需要や政治的な圧力が、他の地域に比べて高まりにくい土壌があると考えられます。
2. 行政の公共交通政策
徳島県や徳島市が策定する地域公共交通計画では、駅単体のハードウェアを更新することよりも、既存の交通ネットワーク全体の持続可能性を確保することが優先されています。
具体的には、バスと鉄道という異なる交通手段をシームレスに連携させる「モーダルミックス」の推進や、利用者が減っている路線でのバスとJRの共同経営(JRのきっぷでバスにも乗れるようにするなど)といった、運用面での改善に力が注がれています。行政の焦点がネットワークの維持・効率化にあるため、高額な投資が必要な自動改札機の設置は、政策的な優先順位が低いのが現状です。

3. バスネットワークの技術的先行
徳島県の交通事情を象徴する動きとして、2026年3月中旬から、徳島バスや徳島市交通局など県内の主要バス路線で、鉄道に先駆けて交通系ICカード「ICOCA」が導入される予定です。
これは、住民の日常の足であるバスの利便性を先に向上させるという現実的な判断であり、鉄道という固定インフラをバスが技術的に「飛び越える(リープフロッグ)」現象と言えます。このバスのICカード化により、地域のキャッシュレス決済の課題が一定程度解決されるため、高コストな鉄道の自動改札機導入を求める声が、かえって弱まる可能性も指摘されています。
四国の他駅との比較

JR四国管内の他の県庁所在地駅と徳島駅を比較すると、同社の段階的かつ戦略的な投資の姿勢が明確に見えてきます。
高松駅(香川県)は、JR四国で最も利用者数が多く収益性も高いことから、早くからICOCA対応の自動改札機が導入されています。さらに、JR四国独自のQRコード乗車券システム「しこくスマートえきちゃん(スマえき)」にも対応しており、完全な近代化が図られています。
一方、松山駅(愛媛県)と高知駅(高知県)は、物理的な自動改札機自体は設置されています。しかし、これらの機械は全国相互利用の交通系ICカードには対応しておらず、主に前述の「スマえき」(QRコード)を読み取るために使用されています。これは、ICカードネットワーク接続という高額な投資を避けつつ、自社システムによる一定の省力化を図る「次善の策」と分析できます。
徳島駅は、このいずれの階層にも含まれず、自動改札機もQRコードリーダーも存在しない、完全な有人改札に留まっています。このインフラの差は、各エリアの利用者数や収益性に基づいた、JR四国の合理的な経営判断の結果と考えられます。
表:四国の県庁所在地中心駅のインフラ比較
| 駅名 | 自動改札機の有無 | 全国交通系ICカード対応 | QRコード(スマえき)対応 |
| 高松駅 | あり | 対応 | 対応 |
| 松山駅 | あり | 非対応 | 対応 |
| 高知駅 | あり | 非対応 | 対応 |
| 徳島駅 | なし | 非対応 | 非対応 |
利用者の反応や口コミ
徳島駅の有人改札に対する利用者の反応や口コミは、立場によって大きく二分される傾向があります。
まず、都市部からの旅行者やビジネス客、特に交通系ICカードの利用に慣れた人々からは、「なぜ県庁所在地の駅なのに自動改札がないのか」「ICカードが使えず不便だ」といった驚きや戸惑いの声が多く聞かれます。きっぷを現金で購入する手間や、財布からICカードを出してしまった時の気まずさなどが、不便さの要因となっているようです。
一方で、地元利用者や鉄道ファンの一部からは、異なる意見も見られます。例えば、「駅員さんとのやり取りが温かい」「昔ながらの風情があって良い」「自動改札機よりスムーズだ」といった、有人改札を肯定的に捉える声です。
このように、効率性や全国標準の利便性を求める声と、地域性や人的な触れ合いを評価する声が混在しているのが、徳島駅の現状に対する反応の特徴と言えます。

旅行者が注意すべきポイント
徳島駅や徳島県内のJR線を利用する旅行者や出張者は、他の地域とは異なる以下の点に注意が必要です。
1. 交通系ICカードは一切使えない
最も注意すべき点です。SuicaやICOCAなどは改札通過にも、きっぷの購入にも使用できません。
2. 現金の準備が必須
乗車券は券売機または「みどりの窓口」で現金で購入する必要があります。特に朝の混雑時などは、時間に余裕を持って駅に到着し、きっぷを購入するようにしてください。クレジットカードが使えるのは「みどりの窓口」のみで、券売機は現金のみ(一部の新型券売機を除く)の場合が多いため、小銭を含めた現金を準備しておくと安心です。
3. きっぷを紛失しない
自動改札機の場合、きっぷは目的地で回収されますが、有人改札では乗車時にスタンプを押されて返却されます。降車時までそのきっぷを紛失しないよう、しっかりと管理する必要があります。もし紛失すると、再度運賃を支払うことになる可能性があります。
4. 乗り換え時間
きっぷの購入に時間がかかることを想定し、乗り換え時間には余裕を持たせることをお勧めします。
将来的に自動改札機は導入される?

徳島駅に将来的に自動改札機が導入されるかについては、現時点(2025年10月)でJR四国や徳島県からの公式な発表はありません。ただし、考えられる将来のシナリオはいくつか存在します。
シナリオA:現状維持(有人改札の継続)
前述したJR四国の財務状況や徳島の交通文化、行政のスタンス、バスのICカード先行導入といった要因が現状維持を強く後押ししています。大きな外部要因の変化がない限り、中期的には有人改札システムが継続される可能性が最も高いと考えられます。
シナリオB:QRコード改札の導入
次善の策として、松山駅や高知駅で採用されている「スマえき」対応のQRコード読み取り専用改札機を導入するシナリオです。これは、全国ICカードネットワークに接続するよりも低コストで設置でき、一定の省力化やデジタル化を実現できるため、JR四国にとっては現実的な選択肢の一つとなり得ます。
シナリオC:完全なICカード対応改札の導入
最もコストがかかるこのシナリオが実現するには、現状の力学を覆すほどの強力なきっかけが必要です。例えば、国民体育大会や大規模な博覧会といった国家的イベントの徳島開催が決定し、県の「玄関口」を刷新するための大規模な予算が組まれる場合などが考えられます。
いずれにしても、短期的な導入の可能性は低く、当面は現在の有人改札が続くと見るのが現実的です。
徳島駅への自動改札機設置の課題と今後
徳島駅の自動改札機未設置問題は、単なる一駅の設備の問題ではなく、人口減少社会における地方交通インフラのあり方を象徴する課題です。
- 徳島駅は全国の県庁所在地JR駅で唯一の完全有人改札
- JR四国で2番目に乗車人員が多い駅にもかかわらず自動改札機がない
- 交通系ICカード(Suica, ICOCAなど)は一切利用不可
- 乗車券は現金で紙のきっぷを購入する必要がある
- 改札は駅係員がきっぷを目視で確認するスタイル
- 未設置の最大の理由はICカードシステム導入の高額なコスト
- JR四国は安全対策やインフラ維持への投資を最優先している
- 徳島県は自家用車中心のクルマ社会である
- 歴史的にJR路線が一度も電化されたことがない
- 鉄道への依存度が低く、近代化の需要が高まりにくい背景がある
- 行政の政策も駅の改修よりバスとの連携を重視
- 2026年3月からバス路線でICOCAが先行導入予定
- 鉄道がバスに技術革新で先行される「リープフロッグ」現象が起きる
- 四国内では高松駅のみがICカードに完全対応
- 松山駅・高知駅はICカード非対応のQRコード改札を導入
- 徳島駅の将来的な導入予定は公式には発表されていない