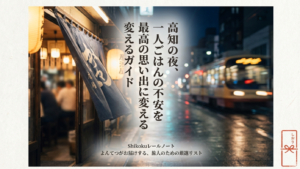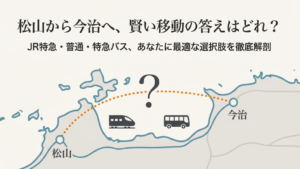予讃線を利用する際、多種多様な予讃線 車両について詳しく知りたいと思ったことはありませんか。特急列車の種類にはどのようなものがあり、代表する特急「しおかぜ」と特急「いしづち」の車両特徴にはどんな違いがあるのでしょうか。また、通勤や通学で利用する普通列車に使われる車両や、風光明媚な松山以西で活躍するディーゼル車両についても気になるところです。
さらに、旅の快適さを左右するグリーン車と座席タイプ、車両ごとの車内設備とサービスの違い、そして特別な旅を演出する観光列車「伊予灘ものがたり」の魅力まで、知りたい情報は尽きません。この記事では、懐かしい過去に走っていた予讃線の車両にも触れながら、今後の予讃線車両の展望も含めて、あなたの疑問に総合的にお答えします。
- 予讃線を走る特急・普通列車の特徴がわかる
- 8000系や8600系など主要車両の違いを比較できる
- 観光列車「伊予灘ものがたり」の楽しみ方がわかる
- 電化区間と非電化区間の車両運用の違いを理解できる
予讃線 車両の主役!特急列車の魅力
- 予讃線を走る特急列車の種類
- 代表する特急「しおかぜ」の車両
- 特急「いしづち」の車両特徴
- 快適なグリーン車と座席タイプ
- 車両ごとの車内設備とサービスの違い
予讃線を走る特急列車の種類

予讃線を走る特急列車は、主に「しおかぜ」と「いしづち」の2種類が運行されています。これらの列車は、本州の岡山や四国の玄関口である高松と、愛媛県の県庁所在地・松山を結ぶ都市間高速輸送という重要な役割を担っています。
使用される車両は、JR四国を代表する8600系電車と8000系電車の2形式が中心です。8600系は新しい技術と快適性を両立させた最新鋭の車両であり、一方の8000系も大規模なリニューアルを経て、現代のニーズに合わせたサービスを提供しています。
また、これらの特急列車には、子供連れの家族から絶大な人気を誇る「アンパンマン列車」も連結されています。外装だけでなく、内装にもアンパンマンの世界が広がる特別仕様の車両が組み込まれており、移動時間そのものを楽しいイベントに変えてくれる存在です。このように、予讃線の特急は、ビジネスや観光といった目的に応じて選べる、多様な車両ラインナップが特徴となっています。
代表する特急「しおかぜ」の車両

特急「しおかぜ」は、岡山駅と松山駅を結ぶ、JR四国の看板列車です。この列車には、主に最新鋭の8600系電車と、大規模リニューアルを実施中の8000系電車が使用されています。(2027年度中に完了予定)
8600系のデザインコンセプトは「レトロフューチャー」で、蒸気機関車を思わせる円形の前面デザインと流線形のフォルムが特徴的です。技術的な最大のポイントは「空気ばね式車体傾斜装置」を採用した点にあります。これは、カーブで車体を傾けることで乗り心地を損なわずに高速走行を可能にするシステムで、従来の振子式に比べてシンプルな構造でメンテナンス性に優れています。
一方、1992年にデビューした8000系は、「制御付自然振子装置」を搭載したJR四国初の特急形電車です。この技術により、予讃線のカーブが多い区間でも大幅なスピードアップを実現しました。デビューから年月が経過しましたが、2023年末から始まったリニューアルにより内外装を一新。8600系に準じたカラーリングとなり、車内設備も全席コンセント設置やWi-Fiサービス導入など、現代のニーズに対応した仕様に生まれ変わっています。
特急「いしづち」の車両特徴

特急「いしづち」は、主に香川県の高松駅と愛媛県の松山駅を結ぶ特急列車です。この列車の最も興味深い特徴は、その効率的な運用方法にあります。多くの「いしづち」は、予讃線の宇多津駅(一部は多度津駅)で、岡山から来る特急「しおかぜ」と連結・分離を行います。
この運用により、高松方面と岡山方面、両方からの利用者が乗り換えなしで松山方面へ向かうことが可能となり、非常に高い利便性を実現しています。使用される車両は「しおかぜ」と同様に8600系と8000系で、連結時には最大で8両編成の長大な特急列車として四国内を走行する姿を見ることができます。
もちろん、全ての「いしづち」が「しおかぜ」と連結するわけではありません。早朝や深夜など一部の時間帯には、「いしづち」が単独で高松・松山間を走行する列車も設定されています。利用する際には、自分が乗る列車がどの区間を走り、どこで連結・分離を行うのかを事前に確認しておくと、よりスムーズな旅行計画が立てられます。
快適なグリーン車と座席タイプ

予讃線の特急列車で、より上質な旅を求める方にはグリーン車の利用がおすすめです。特に8600系とリニューアル後の8000系に設置されているグリーン車は、非常に高い居住性を誇ります。
座席は、通路を挟んで2席+1席の3列配置となっており、普通車よりもパーソナルスペースが格段に広いことが特徴です。定員がごく少数に絞られているため、車内は静かで落ち着いた雰囲気に包まれています。座席にはリクライニング機能や電動レッグレスト、読書灯などが完備されており、長時間の移動でも疲れを感じさせません。
一方、普通車も快適性は十分に確保されています。シートピッチ(座席の前後間隔)は980mmと標準的な寸法ですが、リクライニング機能はもちろん、可動式の枕や大型テーブルが備わっています。リニューアル後の8000系指定席と8600系では全席にコンセントが設置されており、スマートフォンやPCの充電にも困ることはありません。
▼特急車両の座席設備比較
| 項目 | 8600系 グリーン車 | 8000系(リニューアル後) グリーン車 | 8600系 普通車 | 8000系(リニューアル後) 普通車 |
| 座席配置 | 2+1列 | 2+1列 | 2+2列 | 2+2列 |
| シートピッチ | 1,170mm | 1,170mm | 980mm | 980mm |
| コンセント | 全席 | 全席 | 全席 | 指定席:全席, 自由席:窓側 |
| 主な設備 | 電動レッグレスト, 読書灯 | 電動レッグレスト, 読書灯 | 可動式枕, ドリンクホルダー | 大型テーブル, ドリンクホルダー |
| Wi-Fi | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 |
車両ごとの車内設備とサービスの違い

8600系と8000系では、開発された時代の違いから、デビュー当初の車内設備に差がありました。しかし、8000系の大規模リニューアルによって、その差はかなり小さくなっています。
最も大きな違いがあったのは、電源と通信環境です。2014年登場の8600系は、現代のニーズを反映してデビュー時から普通車を含む全席にコンセントを標準装備し、無料公衆無線LAN(Wi-Fi)サービスも提供していました。一方、1992年デビューの8000系には、当初これらの設備はありませんでした。ただ、リニューアル工事によって全席でWi-Fiが利用可能になり、グリーン車・指定席には全席、自由席にも窓側にコンセントが新設され、利便性が飛躍的に向上しています。
バリアフリー設備においても進化が見られます。8600系は最新のガイドラインに準拠しており、広々とした車いす対応の多機能トイレやフリースペースを備えています。8000系もリニューアルに伴い、和式トイレを全て洋式化し、車いす利用者がグループで利用しやすいフリースペースを新設するなど、誰もが快適に利用できる車両へと生まれ変わっています。
多様性が魅力の予讃線 車両ラインナップ
- 普通列車に使われる車両形式一覧
- 松山以西で活躍するディーゼル車両
- 観光列車「伊予灘ものがたり」の魅力
- 過去に走っていた予讃線の車両
- 今後の予讃線車両の展望と期待
- まとめ:個性豊かな予讃線 車両たち
普通列車に使われる車両形式一覧
予讃線の電化区間(高松~伊予市)では、地域の足として活躍する3つの形式の電車が主力となっています。それぞれに開発経緯や特徴が異なり、予讃線の多様な輸送ニーズを支えています。
6000系

1996年に登場した、3両固定編成の近郊形電車です。瀬戸大橋を渡って岡山まで直通する運用を考慮して設計されたため、JR四国の普通列車用車両としては珍しくトイレが設置されています。
車内は転換クロスシートが主体で、快適な座り心地を提供します。
画像:Shikokuレールノート

7000系

予讃線の電化延伸に合わせて開発された、JR四国初のVVVFインバータ制御を採用した車両です。両運転台の7000形と片運転台の7100形があり、1両単位で柔軟に編成を組めるのが最大の強み。
ラッシュ時には長く、閑散時間帯には短くといった、需要に応じたきめ細やかな運用が可能です。
画像出展:写真AC

7200系

国鉄時代に製造された121系電車を、2016年から大規模にリニューアルした車両です。最大の変更点は、足回りを最新のVVVFインバータ制御に交換したことで、最高速度が100km/hから110km/hに向上しました。
この性能向上により、現在では快速「サンポート」の主力車両としても活躍しています。
画像:Shikokuレールノート

松山以西で活躍するディーゼル車両

愛媛県中部の伊予市駅から終点の宇和島駅までは、架線がない非電化区間となり、ディーゼルエンジンで走る気動車(ディーゼル車両)が活躍します。この区間は、美しい海岸線や険しい山々を越えていく、車窓風景の美しいエリアです。
普通列車として主に走っているのは、キハ54形とキハ32形です。これらは国鉄の終わりごろに、地方の閑散路線向けにコストを抑えて製造された「軽快形気動車」です。内装はロングシートでトイレ設備がないなど、非常にシンプルな造りとなっています。厳しい経営環境の中で地域の交通手段を維持するための車両と言えます。
一方で、少し変わった存在がキハ185系です。本来は特急用として造られた車両ですが、新型特急の登場により、一部がこの区間の普通列車として運用されています。そのため、普通運賃でリクライニングシート(固定されている場合あり)の快適な座席に座れる「乗り得列車」として知られています。ただし、普通列車用の編成ではトイレがない場合があるため、長時間の乗車には注意が必要です。

観光列車「伊予灘ものがたり」の魅力

予讃線の魅力を最大限に引き出すために生まれたのが、観光特急「伊予灘ものがたり」です。この列車は単なる移動手段ではなく、乗ること自体が旅の目的となるように設計されています。
車両は、特急用のキハ185系気動車を大胆に改造したもので、コンセプトは「レトロモダン」。2022年にデビューした2代目の現行車両は3両編成となり、貸切で利用できる豪華なグリーン個室も備えています。車内は、美しい伊予灘の海を存分に楽しめるよう、海向きのカウンター席やソファ席が多数配置されています。
この列車のハイライトは、地元の食材をふんだんに使用した食事サービスです。沿線の有名店が監修した料理が、砥部焼などの美しい器で提供されます。また、列車がビュースポットに差しかかると速度を落として走行したり、沿線の人々が手を振ってくれたりと、地域全体で乗客をもてなす温かい雰囲気に満ちあふれています。週末を中心に松山から伊予大洲・八幡浜間を1日4便運行しており、特別な鉄道旅行を体験したい方には最適な列車です。
過去に走っていた予讃線の車両

現在の予讃線で活躍する車両がある一方で、時代の流れとともに走り去っていった数多くの名車両も存在します。これらの車両は、予讃線の近代化の歴史そのものを物語っています。
電化区間の普通列車では、国鉄時代から活躍した113系が長らく主力でしたが、6000系の登場などにより置き換えられました。また、現在7200系として生まれ変わった121系も、原型時代は予讃線の顔として親しまれていました。
特急列車に目を向けると、非電化時代の予讃線を力強く駆け抜けたのがキハ181系やキハ185系です。特にキハ181系による特急「しおかぜ」は、四国の高速化の礎を築きました。その後、世界初の振子式気動車として華々しくデビューしたのが2000系です。カーブを高速で通過できるこの車両の登場は画期的であり、予讃線の所要時間を劇的に短縮しました。現在は後継車両に主役の座を譲りましたが、その功績は大きなものがあります。これらの過去の車両たちが築いた歴史の上に、現在の便利な予讃線があるのです。
今後の予讃線車両の展望と期待
今後の予讃線車両は、大規模な新型車両の導入よりも、既存車両を最大限に活用し、その価値を高めていく方向性が続くと考えられます。
その最も分かりやすい例が、現在進行中の8000系特急電車のリニューアル計画です。新型の8600系と遜色ないレベルまで客室設備を更新することで、特急列車全体のサービス水準を高いレベルで統一しようとしています。また、国鉄時代の121系を改造して快速列車の主力にまで押し上げた7200系の成功例は、今後他の旧型車両を更新する際のモデルケースになる可能性があります。
一方で、JR四国が力を入れているのが観光分野です。大成功を収めている「伊予灘ものがたり」に続く、新たな観光列車の登場も期待されるところです。既存の車両を改造し、その路線ならではの魅力を引き出すユニークな列車が生まれれば、交流人口の拡大にもつながります。厳しい経営環境は続きますが、創意工夫を凝らした車両戦略によって、予讃線の魅力はこれからも進化していくことでしょう。

まとめ:個性豊かな予讃線 車両たち
- 予讃線の特急は主に「しおかぜ」と「いしづち」の2種類
- 主力特急車両は最新鋭の8600系とリニューアルされた8000系
- 8600系は空気ばね式車体傾斜装置で快適な乗り心地を実現
- 8000系は制御付自然振子装置を搭載した高速化のパイオニア
- 8000系は大規模リニューアルでサービスが飛躍的に向上した
- 特急のグリーン車は2+1列のゆとりある豪華な座席配置
- 電化区間の普通列車は6000系・7000系・7200系の3形式
- 7200系は国鉄121系を最新技術で改造した高性能車両
- 松山以西の風光明媚な非電化区間はディーゼル車両が活躍
- キハ54形・32形は地域の足を支えるコストを重視した設計
- 元特急用のキハ185系が普通列車として走ることもある
- 大人気の観光列車「伊予灘ものがたり」は特急列車として運行
- 伊予灘の美しい海岸線の景色と地元の食事が楽しめる
- 子供連れの家族旅行にはアンパンマン列車がおすすめ
- 予讃線では目的や区間に応じた多種多様な車両が活躍している