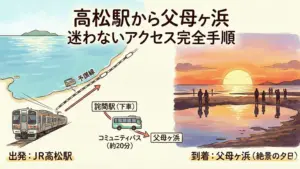JR四国の特急8600系に乗った際、「8600系は乗り心地が悪い」と感じた方や、これから乗る予定で乗り心地が気になる方も多いのではないでしょうか。本記事では、8600系のデメリットとしてよく挙げられる振動と揺れが酷いという声や、座席が硬いという評価、グリーン車の乗り心地の実態など、実際に寄せられた8600系の口コミをもとに詳しく解説します。
さらに、他の特急との比較や車内環境、静音性などについても触れ、乗り心地 評判の背景を多角的に分析します。8600系に乗る前に知っておきたい情報を、利用者目線でわかりやすくまとめました。結論から言えば、個人差があると思いますが少なくとも私は、カーブや通過駅のポイントを高速で通過する際に、揺れは大きめと感じるものの、静かで快適と感じる方が勝ち、乗り心地は概ね良好と感じています。
記事のポイント4つ
- 8600系の乗り心地が悪い原因の具体的内容
- 普通車とグリーン車の乗り心地の違い
- 他の特急との乗り心地や性能の比較ポイント
- 実際の口コミや評価の傾向
8600系は乗り心地が悪いと感じる理由とは?

- 8600系の乗り心地が悪く感じる点について解説
- 振動と揺れが酷い原因とは
- 座席が硬いって本当?
- グリーン車の乗り心地の違い
- 車内環境に関する感想まとめ
8600系の乗り心地が悪く感じる点について解説
JR四国8600系の乗り心地が悪いとされる原因には、技術的な制約やコスト面での妥協が影響しています。特に、採用された「空気ばね式車体傾斜システム」の最大傾斜角度が2度にとどまり、急カーブの多い予讃線では横方向の遠心力を十分に打ち消せないことが指摘されています。
結果として、乗客がカーブ通過時に強い横揺れを感じやすいのがデメリットです。また、こうした傾斜システムの仕様に加えて、予讃線特有の軌道状態や保守状況も関係していると考えられます。線形の良くない区間では、車体の上下左右の揺れが複合的に発生し、それが乗客に不快な振動として伝わることがあります。
さらに、8600系の車体設計では振り子式車両に比べて裾部の絞り込みが少ないため、車両全体のバランスや動きの感覚に違いが出やすいとされ、これも独特の「乗り心地の悪さ」と感じる要因になっているのかもしれません。加えて、乗客の期待値が新型車両ゆえに高かったことも、実際の体感との差を強調し、否定的な評価につながりやすいと考えられます。

振動と揺れが酷い原因とは
振動や揺れが酷いと言われる理由は、車両の傾斜システムの性能だけでなく、運行路線の特徴にもあります。予讃線はカーブが連続する区間が多く、短い間隔で車体が傾斜動作を繰り返す必要があります。しかし、初期の量産先行車では空気供給能力が不足し、傾斜制御が不十分だったことから、突然の横揺れや「ガツン」という衝撃が頻発したとされています。
改良後も根本的な制約は残るため、一定の揺れは避けられない状況です。さらに、カーブ区間では車輪とレールの摩擦音が大きくなり、振動音が車内に伝わりやすいことも不快感の一因となっています。また、短いカーブ間隔では傾斜制御が追いつかず、車体の揺れ戻しが頻発するため、乗客は連続した揺れを感じやすくなります。
こうした複合要素が、8600系の「振動と揺れが酷い」という評判につながっていると考えられます。さらに、台車構造やダンパの仕様など、車両側の設計要素も影響しており、微細な軌道不整による振動が座席や床面を通じて体に直接伝わりやすいとも指摘されています。

座席が硬いって本当?

8600系の普通車座席については、「クッションが薄く硬い」との声が利用者から多く寄せられています。背もたれや座面のクッション性が不足しており、長時間の乗車ではお尻や腰に負担がかかりやすいという不満が見られます。
また、車体の揺れに対する座席のホールド性が低く、横揺れ時に体が左右に振られてしまうことも、乗り心地の悪さを助長している要因といえます。さらに、クッションの薄さは振動吸収性能の低下を意味し、車体の揺れや衝撃を直接体に伝えてしまう可能性があります。長時間座り続ける場合、クッション性の不足が疲労感を早め、体勢を変えたくなるなどの不快感を増幅させることも指摘されています。
加えて、座面の角度や背もたれのサポート範囲が狭いと感じる乗客もおり、体をしっかりと支えきれないことで横揺れ時のストレスがさらに強調される傾向があるようです。座席素材の硬さに加え、足元のスペースやフットレストの有無などの細かい仕様も快適性に影響を与えており、体格によっては「座りにくい」と感じる利用者もいるようです。
グリーン車の乗り心地の違い
一方、グリーン車の座席は普通車よりも高評価を受けています。厚めのクッションやフットレスト・レッグレストが装備されており、直線区間では「快適だった」という感想もあります。ただし、小柄な人には座面が長すぎたり、足元のスペースが狭く感じられたりするケースもあります。
カーブ区間では普通車同様に横揺れを感じるものの、座席のホールド力が高い分、不快感は軽減される傾向にあります。さらに、座席の素材や角度、フットレストの可動域など、細かな人間工学的配慮が快適性に貢献しているとの声もあります。ただ一方で、座面の高さやレッグレストの調整範囲については「もう少し自由度が欲しい」との指摘も見られます。乗客の体型や体格によっては、長時間の乗車で足元の位置に違和感を覚えることもあり、完全な快適性には個人差があるようです。
また、グリーン車では照明の明るさや静音性も評価される要素ですが、走行中の横揺れが読書やPC作業に支障をきたすとの意見もあり、静かさと揺れのバランスに課題が残るという声も寄せられています。加えて、グリーン車の快適性は他の車両との比較に影響されやすく、以前の8000系リニューアル車の座席が不評だったため相対的に高評価されている側面もあると指摘されています。
車内環境に関する感想まとめ
8600系の車内環境については、静かな走行音やコンセントの設置など、設備面では概ね好評を得ています。しかし、揺れの大きさや座席の硬さがマイナス要素として挙げられ、車内で仕事や読書をする際に不便だと感じる乗客も少なくありません。
設備面の充実と乗り心地のギャップが、利用者の評価に二面性をもたらしているとも言えるでしょう。加えて、Wi-Fiや照明、車内の温度管理といったサービス面の評価も分かれており、設備は整っていても根本的な快適性が揺れに左右されるという課題が見受けられます。
8600系は乗り心地が悪いと言う口コミについて検証

- 8600系の口コミをチェック
- 乗り心地 評判は賛否両論?
- 他の特急との比較ポイント
- 静音性は期待できる
8600系の口コミをチェック
インターネット上では、8600系の乗り心地について多くの口コミが投稿されています。「揺れが激しい」「カーブで体が振られる」といった否定的な意見が目立つ一方、「静かで快適」「直線区間では問題ない」といった肯定的な声も存在します。
特に、初期に未改良の量産先行車に乗車した人の間で、否定的な評価が広まりやすかった傾向が見られます。こうした口コミの中には、体調や感受性の個人差によるものも含まれており、万人に共通する体験とは限らないことも指摘されています。
乗り心地 評判は賛否両論?
8600系の乗り心地に対する評判は、乗車区間や座席の種類によって大きく異なります。直線区間やグリーン車では高評価が見られる一方、カーブの多い区間や普通車では不満の声が多い傾向です。技術的な改良が進められたものの、路線特性や構造上の限界から「完全な快適性」は難しいとの見方もあります。利用者の期待値の高さも、評価に影響している可能性があります。さらに、振り子式車両との比較を前提に語られることが多いため、相対的に厳しい評価になりやすい側面もあります。
他の特急との比較ポイント

乗り心地の評価を考える際、8000系(振り子式)や2000系気動車との比較は避けられません。8000系では最大5度の車体傾斜が可能で、カーブ通過時の遠心力をより効果的に軽減できました。これに対し、8600系は最大2度の傾斜にとどまるため、同じ区間でも横方向の力を強く感じやすいとされます。
過去の車両との比較が、乗客の「以前の方が良かった」という印象を生む要因となっています。さらに、比較対象の車両が「揺れの質」において異なる特徴を持つことから、8600系特有の揺れ方が違和感として認識されやすいという指摘もあります。
静音性は期待できる?
8600系の静音性については、走行音が静かであると肯定的に評価されることが多いです。特に高速走行時や直線区間では、「他の特急より静か」と感じる利用者もいます。ただし、カーブやポイント通過時の衝撃音や台車の動きによる振動音が耳につく場面もあり、全体的な静音性の評価にはばらつきがあります。
揺れによる不快感が、静音性の印象に影響することも少なくありません。さらに、車内の静けさがかえって揺れや振動を際立たせてしまうという意見もあり、静音性の評価には複雑な側面があるといえます。また、周囲の会話やアナウンスの響きやすさが気になる乗客もおり、音響設計そのものが静かさと快適さに両面から影響していると指摘されています。
加えて、音の静けさゆえに車内での物音や車体からの微振動音が目立ちやすくなり、意識がそちらに向いてしまうこともあるようです。こうした理由から、静音性が高いことは必ずしも全ての乗客にとって快適さを保証するわけではなく、個人の感覚や使用目的によって評価が分かれるポイントといえます。
8600系は乗り心地が悪いと言われる理由の総括
- 空気ばね式車体傾斜システムの傾斜角が2度に制限されている
- 予讃線の急カーブでは遠心力を十分に相殺できない
- 車体の上下左右の揺れが複合的に発生しやすい
- 振り子式車両に比べ車体設計が揺れに弱い傾向にある
- 新型車両への期待が高く評価が厳しくなりやすい
- 短いカーブ間隔では傾斜制御が追いつかない
- 空気供給不足により傾斜動作が不安定になることがある
- 車輪とレールの摩擦音が車内に響きやすい
- 台車構造やダンパ性能が微細振動を拾いやすい
- 普通車座席のクッションが薄く長時間乗車で疲れやすい
- 座席のホールド性が低く横揺れ時に体が振られやすい
- グリーン車はホールド力が高く普通車より快適とされる
- グリーン車の座面長やレッグレスト調整に不満がある
- 設備面は充実しているが揺れが快適性を損ねる
- 静音性の高さが逆に揺れや微振動を際立たせることがある