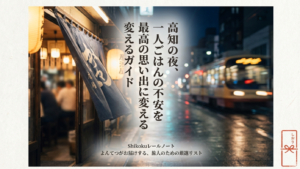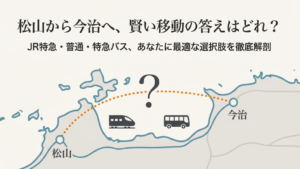JR四国が近年、全社的に導入を進めている「パターンダイヤ」について、関心をお持ちではないでしょうか。JR四国のパターンダイヤとは何か、その概要から知りたい方もいらっしゃるでしょう。また、JR四国での導入背景にはどのような事情があるのか、具体的な路線別の運行パターンはどう変わるのか、といった点も気になるところです。
この記事では、特急列車のパターンダイヤ化や普通列車の運行間隔の変更点、それによって生まれる利用者メリットと混雑緩和の効果を詳しく解説します。同時に、ダイヤ作成の課題と制約、他社・他地域との比較を通じて見える特徴にも触れていきます。今後の改善・拡充計画や、この取り組みが示すJR四国の将来ビジョンまで、網羅的に掘り下げていきますので、ぜひ最後までご覧ください。
- パターンダイヤの基本的な仕組みとJR四国が導入した理由
- 予讃線や土讃線など主要路線での具体的な変更点
- 利用者にとってのメリットと、所要時間などの注意点
- 今後の展開と四国の鉄道が目指す未来の姿
JR四国のパターンダイヤ戦略の全体像
- そもそもパターンダイヤの概要とは
- JR四国での導入背景にある経営戦略
- 利用者メリットと期待される混雑緩和
- ダイヤ作成の課題と避けられない制約
- 他社・他地域との比較で見る特異性
|
|
そもそもパターンダイヤの概要とは

パターンダイヤとは、特定の時間帯において、毎時同じような時刻に列車が発車・到着するように運行間隔をそろえるダイヤ編成の手法を指します。例えば、「普通列車は毎時15分と45分に発車する」といったように、運行時刻がパターン化されるため、利用者は時刻表を細かく確認しなくても、直感的に列車のおおよその発車時刻を把握できます。
この手法の最大の目的は、利用者の「わかりやすさ」を向上させることです。不規則な間隔で運行されるよりも、等間隔で運行される方が、利用計画を立てやすくなります。特に日中の閑散時間帯などに導入されることが多く、限られた運行本数であっても、予測可能性を高めることで利便性を維持する狙いがあります。
JR四国では、この基本的なパターンダイヤの考え方をさらに発展させた「タクトダイヤ」という概念も導入しています。「タクト」とは指揮棒を意味し、主要な乗り換え駅で、複数方面の列車がほぼ同時に到着し、短い待ち時間でスムーズに乗り換えられるよう、相互の接続を同期させるダイヤを指します。これにより、駅は単なる通過点から、路線網全体の利便性を高めるハブとしての機能を持つようになります。
JR四国での導入背景にある経営戦略
JR四国がパターンダイヤを全社的に導入する背景には、同社が直面する極めて厳しい経営環境と、それに対応するための明確な経営戦略が存在します。これは単なるサービス改善策ではなく、会社の生存を賭けた根源的な取り組みと位置づけられています。
最大の理由は、抜本的なコスト効率化の実現です。人口減少やコロナ禍を経ても回復しきらない利用状況、そして深刻化する乗務員不足といった課題に対応するため、運行体系そのものを見直す必要がありました。パターンダイヤを導入する過程で、利用が低迷している列車や、運行が非効率な系統を整理・削減し、経営資源をより利用者の多い区間や時間帯に集中させることが可能になります。
また、これはJR四国が掲げる「四国に最適で持続可能な公共交通ネットワーク『四国モデル』」を確立するための中核的な施策です。絶対的な運行本数を減らすという厳しい現実を、パターン化による「わかりやすさ」や「覚えやすさ」という付加価値で補い、利用者へのマイナスイメージを和らげる狙いがあります。つまり、「管理された縮小」を、利用者や沿線自治体にとって受け入れやすい「戦略的な最適化」として再定義するための、高度なコミュニケーション戦略でもあるのです。
利用者メリットと期待される混雑緩和

パターンダイヤの導入は、利用者にとって多くのメリットをもたらします。最大の利点は、前述の通り、鉄道が格段に使いやすくなることです。毎時同じ時刻に列車が来るという「予測可能性」は、精神的な負担を大きく軽減します。お出かけの際に、いちいち分厚い時刻表をめくったり、何度も検索したりする必要がなくなるのは、日々の利用者にとって大きな変化です。
鉄道総合技術研究所の研究によれば、運行間隔をパターン化することは、利用者の待ち時間を心理的に短縮させ、場合によっては列車を増発したのと同等の利便性向上効果をもたらすとされています。これは、新たな車両や設備投資を最小限に抑えつつ、サービスの質を高めることができる「仮想的な増発」と考えることができます。
さらに、運行間隔が均等になることで、特定の列車への利用者の集中を緩和する効果も期待できます。これまでは、次の列車まで2時間も空くような時間帯があると、その前の列車に利用者が集中しがちでした。しかし、例えば1時間間隔が保証されれば、利用者は自分の都合の良い方の列車を選ぶことができ、混雑の平準化につながります。
ダイヤ作成の課題と避けられない制約
一方で、パターンダイヤの導入はメリットばかりではありません。整然としたダイヤを実現するためには、そのリズムを乱す不規則な要素を排除する必要があり、利用者にとって不利益となる側面も生まれます。
最も大きな課題は、既存の便利なサービスが廃止される可能性がある点です。例えば、2025年改正では岡山駅へ直通していた特急「うずしお」が廃止され、利用者は高松駅での乗り換えが必須となりました。これは、高松~徳島間のシンプルなパターンを構築するためには避けられない選択でしたが、直通の利便性を享受していた利用者にとっては明確なサービス低下となります。
また、パターン化によって所要時間が延びるケースもあります。定時運行を維持し、遅延を波及させないために、駅での停車時間に余裕を持たせる「寝かせたダイヤ」が組まれることがあります。速達性を少し犠牲にしてでも、わかりやすさと定時性を優先するという判断です。
さらに、予土線のような超ローカル線では、パターン化と引き換えに絶対的な運行本数が削減されるという厳しいトレードオフが発生します。2時間に1本という完全に予測可能なダイヤは、見方を変えれば「最大2時間の待ち時間」を意味し、利便性が向上したとは一概に言えない状況も生まれるのです。
他社・他地域との比較で見る特異性
パターンダイヤ自体は、全国の多くの鉄道事業者で採用されている一般的な手法です。しかし、JR四国の取り組みは、他社の事例と比較すると、その「適用範囲の広さ」と「徹底度」において際立っています。
例えば、JR九州も九州新幹線や主要な在来線特急でパターンダイヤを導入し、接続の改善やわかりやすい1時間間隔の運行を実現しています。また、JR北海道では、主に札幌都市圏の高頻度路線である快速「エアポート」などで重点的に導入されています。このように、他社ではパターンダイヤを都市圏や主要幹線における有効な「ツール」の一つとして活用するケースがほとんどです。
これに対して、JR四国の戦略は、パターンダイヤを経営の根幹をなす「哲学」として採用している点が特異です。その適用範囲は、高松や松山といった都市圏だけでなく、四国屈指の閑散線区である予土線にまで及んでいます。これは、同社が直面する経営上のプレッシャーが他社よりも格段に大きく、より大胆で包括的な改革を迫られていることの表れと考えられます。一部の路線や列車を最適化するだけでは不十分で、会社全体の運行システムを根底から再構築しようという強い意志がうかがえるのです。
|
|
路線から見るJR四国のパターンダイヤ
- 主要な路線別の運行パターンを解説
- 利便性を高める特急列車のパターンダイヤ化
- 普通列車の運行間隔と利便性の変化
- 今後の改善・拡充計画と注目ポイント
- JR四国の将来ビジョンを支える戦略
- 総括:JR四国パターンダイヤの今後
主要な路線別の運行パターンを解説

2025年3月のダイヤ改正は、JR四国のパターンダイヤ戦略の集大成と位置づけられ、島内のほぼ全域にわたって運行体系が大きく変わります。ここでは、主要な路線でどのような運行パターンが導入されるのか、その概要を解説します。
表:2025年3月ダイヤ改正における主なパターンダイヤ導入概要
| 路線名 | 区間 | 主な変更内容 |
| 予讃線 | 高松~多度津 | パターンダイヤ時間帯を11時~19時台に拡大 |
| 伊予西条~松山 | 昼間帯を中心に主要駅の普通列車発車時刻を統一 | |
| 松山~宇和島 | 特急・普通列車ともに10時~19時台でパターン化 | |
| 土讃線 | 特急「南風」 | 主要駅での発車時刻をパターン化 |
| 土佐山田~高知 | パターンダイヤ時間帯を9時~17時台に拡大 | |
| 高徳線 | 高松~引田 | パターンダイヤ時間帯を9時~19時台に拡大 |
| 鳴門線 | 全線 | パターンダイヤ時間帯を9時~19時台に拡大 |
| 牟岐線 | 徳島~阿南 | パターンダイヤ時間帯を9時~20時台に拡大 |
| 予土線 | 江川崎~宇和島 | 概ね2時間間隔のパターンダイヤを導入 |
各路線の特徴
予讃線では、高松都市圏での利便性向上に加え、長年の課題であった松山エリアで遂に本格的なパターンダイヤが導入されます。これは2024年9月の松山駅高架化という大規模なインフラ整備が完了したことで初めて可能になったもので、ハードウェアへの投資がダイヤ編成の自由度を高めた典型例です。
土讃線では、普通列車だけでなく、基幹特急である「南風」自体がパターン化の対象となるのが大きな特徴です。これにより、岡山・高松と高知を結ぶ大動脈の予測性が大きく向上します。
徳島を中心とするエリアでは、すでに導入されていたパターンダイヤがさらに強化・拡大され、日中のほぼ全ての時間帯で規則的な運行が実現します。
利便性を高める特急列車のパターンダイヤ化

今回の改正では、普通列車だけでなく、多くの特急列車にもパターンダイヤの考え方が導入され、利便性と予測性の向上が図られます。
特に象徴的なのが、土讃線を走る特急「南風」です。多度津、琴平、阿波池田といった主要駅の発車時刻がパターン化され、例えば高知駅では毎時30分頃に岡山行きが発車するなど、非常にわかりやすくなります。これまでのように、列車によって発車時刻がバラバラという状況が解消され、ビジネスや観光での利用計画が立てやすくなるでしょう。
また、高徳線を走る特急「うずしお」では、使用する車両を性能の良い新型車両(2600系・2700系)に統一する取り組みが行われます。これにより、列車ごとの速度のばらつきがなくなり、所要時間が安定します。車両性能の標準化は、正確で信頼性の高いパターンダイヤを組む上での大前提であり、ソフトウェアであるダイヤとハードウェアである車両が一体となってサービス向上を実現する好例です。同時に、日中の「うずしお」の停車駅も統一され、わかりやすさが一層向上します。

普通列車の運行間隔と利便性の変化
普通列車の運行間隔も、パターンダイヤ導入によって大きく変わります。高松、高知、徳島といった県庁所在地周辺の都市圏では、パターンダイヤが適用される時間帯が拡大され、日中の移動が一層便利になります。
一方で、大きな議論を呼んでいるのが、予土線(宇和島~江川崎間)へのパターンダイヤ導入です。この区間では、早朝・夜間を除き、運行間隔が概ね2時間に統一されます。これまで運行間隔が3~5時間も空くことがあった不規則なダイヤと比べれば、完全に予測可能になるというメリットはあります。
しかし、これは利用者に対して明確な選択を提示するものでもあります。つまり、「本数は減っても2時間に1本必ず来るわかりやすさ」と、「不規則でも今より本数が多い方が良い」という価値観の対立です。特に通院や買い物などで鉄道を利用する地域住民にとっては、待ち時間が長くなるという側面が大きく、手放しで利便性向上とは言えないのが実情です。この事例は、パターンダイヤ戦略が内包するメリットとデメリットのトレードオフを最も先鋭的に示しています。
今後の改善・拡充計画と注目ポイント
JR四国のパターンダイヤ戦略は、2025年3月の改正で一つの頂点を迎えますが、これが終わりではありません。むしろ、全社的な基盤が整ったここからが、真のスタート地点とも考えられます。
注目すべきポイントの一つは、徳島駅で導入されている「タクトダイヤ」のさらなる深化です。これは単一の路線だけでなく、複数の路線が結節する駅で乗り換えの利便性を最大化する試みであり、ネットワーク全体の効率を高める上で鍵となります。この思想が、将来的には多度津駅や松山駅など、他の主要な乗り換え駅にも応用されていく可能性があります。
また、パターンダイヤの導入は、バスなどの他の交通機関との連携を促す「触媒」としての役割も担います。鉄道の時刻が予測可能になることで、バスの接続ダイヤが組みやすくなります。徳島県の牟岐線沿線で始まった鉄道とバスの「共同経営」モデルは、まさにその先進事例です。鉄道が担うべき基幹部分と、バスが補うべき地域内輸送部分の役割分担を明確にし、地域全体で持続可能な交通網を構築していく上で、パターンダイヤは不可欠な土台となるのです。
JR四国の将来ビジョンを支える戦略

JR四国が推進する一連のパターンダイヤ戦略は、その場しのぎの対策ではなく、長期的な将来ビジョンに基づいたものです。同社が掲げる「長期経営ビジョン2030」や「中期経営計画2025」では、2031年度の経営自立という極めて高い目標が設定されています。
この目標を達成するためには、徹底した経営の効率化が不可欠です。パターンダイヤの導入は、運行系統の単純化によるコスト削減や、乗務員運用の効率化に直結します。特急「宇和海」の一部区間でのワンマン運転導入や、駅の無人化といった施策も、この大きな流れの中に位置づけられます。限られた人的・物的資源を最大限有効に活用し、会社を持続させていくための、いわば「選択と集中」の戦略です。
そして、この戦略は「四国モデル」の構築というビジョンに集約されます。これは、ただ鉄道事業を縮小するのではなく、鉄道を地域交通の「背骨」と位置づけ、バスなど他の交通モードとの連携を強化することで、四国という地域に最適化された、効率的で持続可能な公共交通ネットワークを再構築しようという壮大な構想です。パターンダイヤは、その背骨のリズムを整え、ネットワーク全体を機能させるための心臓部とも言える役割を担っているのです。
総括:JR四国のパターンダイヤの今後
この記事では、JR四国が全社的に推進するパターンダイヤ戦略について、その概要から具体的な内容、そして背景にあるビジョンまでを多角的に解説しました。最後に、本記事の要点を以下にまとめます。
- パターンダイヤは毎時同じ時刻に列車が発着する運行形態
- 利用者のわかりやすさ向上と経営効率化が主な目的
- JR四国の生存を賭けた根源的な経営戦略と位置づけられる
- 2019年の徳島エリアでの実験的導入から始まった
- 2025年3月改正で予土線を含むほぼ全域に拡大される
- 松山エリアへの導入は松山駅の高架化事業完了が前提条件だった
- 特急「南風」もパターン化の対象となり予測性が向上
- 特急「うずしお」は車両統一で運行の安定性を高めた
- 予土線では2時間間隔のパターンが導入される
- メリットは予測可能性の向上と混雑の平準化
- デメリットは一部列車の廃止や所要時間の延伸
- 岡山直通「うずしお」の廃止は利便性が低下する一面も
- パターン化はバスなど他交通機関との連携を促す触媒となる
- 「四国モデル」という持続可能な交通網構築の中核をなす
- わかりやすさと引き換えに失われるサービスとのバランスが今後の課題