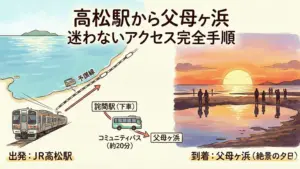JR四国の特急「しおかぜ」「いしづち」の違いってなんだろう?それは、岡山や高松から松山方面へ向かう際の列車選びで、疑問や不安を感じているのではないでしょうか。この二つの列車の、しおかぜといしづちの運行区間の違いや、具体的な停車駅比較、さらには車両編成と座席の違いについて、詳しい情報をお探しなのかもしれません。
また、それぞれの所要時間と速達性の違い、旅の計画で鍵となる乗り換えポイント、自由席・指定席の利用しやすさ比較、気になる料金の違い、そして何より快適性・サービス内容の比較まで、知りたいことは多岐にわたるはずです。これらの違いを正確に理解しないまま予約してしまうと、思わぬ不便を感じてしまう可能性もあります。
この記事では、JR四国が誇る二つの特急列車が織りなす、合理的で少し複雑な運行システムを徹底的に解き明かし、あなたの旅がより快適でスムーズなものになるよう、全ての疑問に明確にお答えします。
- 運行ルートや役割といった基本的な違い
- 併結・分割運転の仕組みと乗り換えの注意点
- 車両ごとの座席やコンセントなどサービスの違い
- あなたの旅の目的に最適な列車の選び方
基本から解説!特急しおかぜ・いしづちの違い

- しおかぜといしづちの運行区間の違い
- 停車駅比較でわかるそれぞれの役割
- 所要時間と速達性の違いを解説
- 旅の鍵となる便利な乗り換えポイント
- 知っておきたい車両編成と座席の違い
しおかぜといしづちの運行区間の違い
特急「しおかぜ」と「いしづち」の最も根本的な違いは、その運行区間と、それによって定められた役割にあります。
「しおかぜ」は、本州の岡山駅と愛媛県の松山駅を結ぶ列車です。一方、「いしづち」は四国内の主要都市である香川県の高松駅と松山駅を結んでいます。このように、起点が岡山か高松か、というのが最大の違いです。
この背景には、それぞれの列車が担う戦略的な役割があります。「しおかぜ」の主な目的は、山陽新幹線と接続し、本州と四国西部を結ぶ広域輸送を担うことです。瀬戸大橋を渡るルートは、まさにその象徴と言えます。対して「いしづち」は、香川県と愛媛県の県庁所在地間を結ぶ、四国内のビジネスや観光の動脈としての役割を担っています。
要するに、「しおかぜ」は四国の玄関口として外と内を繋ぐ列車、「いしづち」は四国内の移動を支える列車、と考えると分かりやすいでしょう。
| 特徴 | 特急「しおかぜ」 | 特急「いしづち」 |
| 主要運行区間 | 岡山 ↔ 松山 | 高松 ↔ 松山 |
| 戦略的役割 | 本州連絡(新幹線接続) | 四国内都市間輸送 |
| 経由する主な橋 | 瀬戸大橋 | なし |
| 名称の由来 | 瀬戸内海の「潮風」 | 愛媛県の「石鎚山」 |
停車駅比較でわかるそれぞれの役割
前述の通り、しおかぜといしづちでは運行区間が異なりますが、停車駅のパターンからも、それぞれの役割の違いが明確に見て取れます。
岡山駅を出発した「しおかぜ」は、本州側の児島駅に停車した後、瀬戸大橋を渡り、四国の宇多津駅に至ります。この区間は、新幹線からの乗り継ぎ客を迅速に四国へ運ぶため、停車駅が最小限に絞られています。
一方、高松駅を出発した「いしづち」は、坂出駅などに停車しながら宇多津駅へ向かいます。この区間は、香川県内の主要な町からの利用客を拾い上げる役割を担っています。
そして、二つの列車が出会うのが宇多津駅です。ここから終点の松山駅までは、多くの場合、二つの列車が連結して一つの列車として走るため、基本的な停車駅(多度津、観音寺、伊予三島、新居浜、伊予西条、今治など)は共通になります。このため、宇多津駅より西の区間では、どちらの特急に乗っても停車パターンに大きな差はありません。
このように、宇多津駅を境にして、それぞれの列車が異なるエリアの需要を分担していることが、停車駅のパターンからもうかがえます。
所要時間と速達性の違いを解説
所要時間と速達性については、単純な比較が難しい側面があります。なぜなら、二つの列車は起点が異なり、走行距離そのものが違うからです。
岡山駅から松山駅までの「しおかぜ」の所要時間は、おおよそ2時間40分から2時間50分程度です。これに対し、高松駅から松山駅までの「いしづち」は、約2時間20分から2時間30分ほどで結びます。
注意したいのは、宇多津駅から松山駅までの区間では、両列車は併結されて同じ速度で走るため、この区間における速達性に違いはないということです。したがって、「どちらが速いか」という問いは、「どの駅から乗るか」によって答えが変わります。
また、一部の「いしづち」には、高松~松山間を単独で運行する列車があり、100番台の号数が付けられています。これらの列車は、途中で「しおかぜ」との連結作業がないため、若干スムーズに運行される場合がありますが、所要時間に大きな差は生まれません。
旅の計画を立てる際は、単純な速さよりも、自分の出発地に合った列車を選択することが大切になります。
旅の鍵となる便利な乗り換えポイント
「しおかぜ」と「いしづち」を語る上で避けて通れないのが、大半の列車で行われる連結・分割(併結・分割)運転です。この運用の中心となるのが香川県の宇多津駅です。
通常時の運用:宇多津駅が中心
松山方面へ向かう下り列車の場合、まず岡山からの「しおかぜ」が宇多津駅で待機し、後から来た高松からの「いしづち」と連結して出発します。逆に、岡山・高松方面へ向かう上り列車は、宇多津駅で分割され、「いしづち」が先に高松へ、「しおかぜ」がその後を岡山へと向かいます。自分の乗る車両を間違えると目的地に着けないため、乗車前に切符の号車番号を必ず確認することが求められます。
例外運用時の注意点:乗り換え駅が変わる
ただし、ゴールデンウィークやお盆、年末年始などの繁忙期や、車両検査の際にはこの併結運転が中止されることがあります。この場合、岡山~松山間は全車両が「しおかぜ」として運行され、「いしづち」の利用者は途中で乗り換えが必要になるため、注意が必要です。
この乗り換え駅は、移動方向によって異なるという、非常に合理的なルールが存在します。
- 下り(高松から松山方面へ):乗り換えは多度津駅
- 上り(松山から高松方面へ):乗り換えは宇多津駅
これは、本州連絡という最重要任務を担う「しおかぜ」の定時運行を最優先するための措置です。上りでは、宇多津駅で分割すれば「しおかぜ」がスムーズに瀬戸大橋線に入れます。一方、下りでは、「しおかぜ」を宇多津駅で待たせることなく直進させるため、「いしづち」側が先の多度津駅までシャトル運行し、そこで乗り換えてもらう形式をとります。
この例外運用を知らずにいると、乗り換え時に混乱する可能性があるため、特に繁忙期に利用する際は運行情報を確認しておくと安心です。

知っておきたい車両編成と座席の違い
併結運転を行う「しおかぜ」と「いしづち」では、乗車する号車を間違えないことが極めて大切です。
基本的な編成として、8000系電車で運行される場合、「しおかぜ」(岡山行き)が1号車から5号車、「いしづち」(高松行き)が6号車から8号車で構成されるのが一般的です。新しい8600系電車の場合は、「しおかぜ」が5両、「いしづち」が2両といった組み合わせが多く見られます。
上り列車(松山発)に乗る際、例えば高松へ向かう切符を持っているのに、誤って1号車から5号車の「しおかぜ」車両に乗ってしまうと、宇多津駅で列車が分割された後、岡山へ向かってしまいます。ホームの電光掲示板やアナウンスでは、行き先ごと乗車位置が案内されていますので、乗車前には自分の切符に書かれた号車と行き先を必ず確認する習慣をつけましょう。
予約システム上は、例えば高松から今治まで乗る場合でも、切符は1枚で発券され、宇多津での乗り継ぎは意識する必要はありません。しかし、物理的にはどの車両に乗るかが行き先を決定づけるため、この編成のルールは利用者にとって最も注意すべき点の一つと言えます。
乗客視点で比べる特急しおかぜ・いしづちの違い

- 料金の違いはグリーン車の有無
- 電源は?快適性・サービス内容の比較
- 自由席・指定席の利用しやすさ比較
料金の違いはグリーン車の有無
特急料金や運賃は、乗車する距離に応じて決まるため、「しおかぜ」と「いしづち」で料金体系が異なるわけではありません。同じ区間に乗車する場合、普通車であれば料金は同額です。
しかし、両者にはサービスレベルにおける決定的な料金の違いが存在します。それは、上級クラスである「グリーン車」の有無です。
グリーン車は、原則として「しおかぜ」の編成(通常は1号車)にのみ設定されています。より広く快適な座席で旅をしたい場合、必然的に「しおかぜ」のグリーン席を予約することになります。一方、「いしづち」は基本的に普通車のみで構成されており、グリーン車の設定はありません(ただし一部の列車に設定あり)。
したがって、高松から乗車する利用者が、併結される列車でグリーン車を利用したい場合は、宇多津駅で「しおかぜ」のグリーン車に移動する必要があります(その区間のグリーン券が別途必要)。岡山から乗車する利用者は、そのまま松山までグリーン車の快適な旅を楽しむことができます。(いしづち1号など一部列車は例外で、グリーン車あり)
このように、基本的な料金に差はありませんが、提供されるサービスクラスの選択肢に明確な違いがあるのです。
電源は?快適性・サービス内容の比較
乗客の快適性を左右する車内設備、特に電源コンセントの有無は、使用される車両によって大きく異なります。現在、「しおかぜ」「いしづち」には主に2種類の車両が使われており、どちらに当たるかで体験が変わります。
モダンで快適な8600系
2016年頃から導入された比較的新しい車両です。蒸気機関車をモチーフにした角張ったデザインが特徴で、最大のメリットは、通路側を含めた全ての座席にモバイル用電源コンセントが設置されている点です。また、可動式の枕やフットレストも備わり、現代のニーズに応えた快適な空間を提供しています。座席はやや硬めとの評価もありますが、電源を確実に確保したい場合は、この8600系で運行される列車を選ぶのが最も確実です。
リニューアルが進む8000系
1990年代に登場した伝統的な振子式車両です。長年、電源コンセントがないことが弱点でしたが、2023年度から大規模なリニューアルが進行中です。リニューアル後の車両では、座席の快適性はそのままに、設備が大幅に向上しました。
- リニューアル後の8000系:
グリーン車と普通車指定席は全座席にコンセントが設置されます。しかし、自由席(4~7号車)は窓側の席にしか設置されません。座席は伝統的に柔らかめで、長時間の乗車でも疲れにくいと評価されています。 - 未更新の8000系:
コンセントは設置されていません。この車両に当たった場合、モバイルバッテリーが必須となります。
以上のことから、乗車する列車がどの車両で運行されるかは、快適性を大きく左右する要素です。
| 車両形式 | 電源コンセント(指定席) | 電源コンセント(自由席) | 座席の快適性(主観) |
| 8600系 | 全席に設置 | 全席に設置 | 硬め・モダン |
| 8000系(リニューアル後) | 全席に設置 | 窓側席のみ | 柔らかめ・伝統的 |
| 8000系(未更新) | なし | なし | 柔らかめ・伝統的 |
自由席・指定席の利用しやすさ比較

自由席と指定席の選択は、単に座席が確保されるかどうかだけの問題ではありません。前述の通り、車両によってはサービス内容に明確な差が生じるため、利用のしやすさにも影響を与えます。
8600系で運行される列車であれば、自由席でも指定席でも全ての座席にコンセントがあるため、サービス内容に差はありません。この場合は、確実に座りたいか、少しでも料金を抑えたいか、という純粋な判断で選ぶことができます。
一方で、リニューアルされた8000系の列車に乗車する場合は、この選択がより重要になります。指定席を予約すれば、どの席に当たってもコンセントが利用できるため、スマートフォンの充電などを気にする必要がありません。しかし、自由席を選んだ場合、コンセントがあるのは窓側の席のみです。混雑時に通路側の席しか空いていなかった場合、目的地まで電源なしで過ごすことになります。
したがって、8000系での移動が予想され、かつ道中でPC作業やスマートフォンの充電が不可欠な場合は、追加料金を払ってでも指定席を確保する価値は十分にあると考えられます。逆に、乗車時間が短い、あるいはバッテリーに余裕がある場合は、自由席で柔軟に旅をするのも良い選択です。
このように、利用する車両タイプを考慮に入れた上で自由席か指定席かを選択することが、快適な旅の鍵となります。

まとめ:旅の目的に合う列車を選ぶための違い
ここまで解説してきた「特急しおかぜ」と「いしづち」の違いについて、最後に重要なポイントをまとめます。あなたの次の旅行計画の参考にしてください。
- しおかぜは岡山と松山を結ぶ本州連絡特急
- いしづちは高松と松山を結ぶ四国内都市間特急
- 役割の違いが運行区間と起点の違いに直結している
- 基本的には宇多津駅で連結・分割して運行される
- 繁忙期など例外時には乗り換えが発生することがある
- 例外時の乗り換え駅は進行方向で異なるので注意が必要
- 普通車の基本料金は同じ区間ならどちらも同じ
- 料金の大きな違いはグリーン車の有無
- グリーン車はしおかぜ編成の1号車にのみ連結(一部例外あり)
- 快適性は8600系と8000系のどちらの車両かで大きく変わる
- 確実に電源を使いたいなら8600系が最もおすすめ
- 8000系リニューアル車は指定席なら全席に電源あり
- 8000系リニューアル車の自由席は窓側席のみ電源がある
- 未更新の8000系には電源コンセントがない
- 乗車時は自分の切符の号車番号を行き先と照合することが不可欠
- 号車を間違えると分割後に違う目的地へ行ってしまうリスクがある
- これらの違いを理解すれば旅の計画がよりスムーズになる